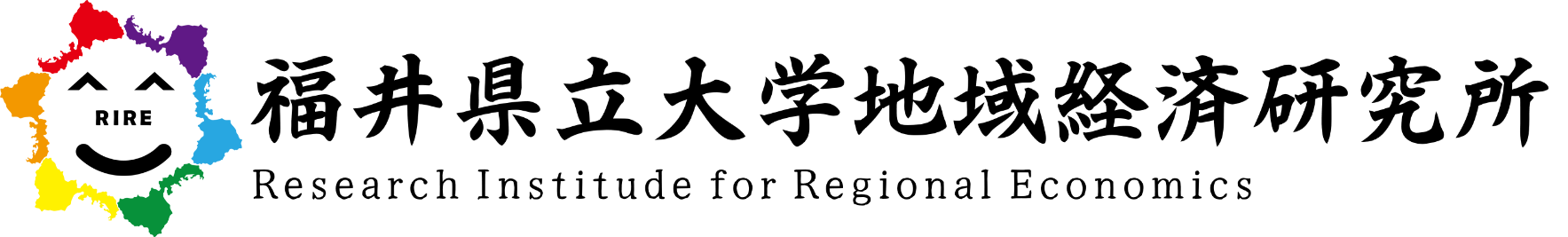メールマガジン
南越前町、今庄地区にみる地域おこし
福井県中央部にある南越前町。この地は、海(河野地区)と山(今庄地区)、里(南条地区)といった三つの地区それぞれに固有の特徴を持つ人口1万人あまりの小さな町でもある。その中で今庄地区は、大半が山間地だけに、その厳しい環境を活かした蕎麦の栽培が盛んで、現在も「今庄そば」はこの地区一番の特産品として知られている。一説では、同地区の蕎麦は、約4百年前の慶弔6年、府中(現在の越前市)に赴任した本多富正公が京都伏見から「そば職人」を呼び寄せ、城下の人々の非常食として栽培させるとともに、大根おろしを蕎麦にかけ食べることを奨励、それが福井の「おろし蕎麦」の始まりだとも言われている。当地は季節の変化にともない寒暖の差が激しく、雪どけの良質の水に恵まれるとともに、霧が深い山間地はよい蕎麦を生む最適な環境を備えた場所であったことも蕎麦づくりが盛んとなった所以かも知れない。
ところで、今庄地区と言えば、江戸時代に近江米原(滋賀)より越前今庄(福井)を経て、直江津(新潟)につながる北国街道の宿場町として栄えた地でもある。当地にあって古くから幾重にも重なる南条山地は北陸道最大の難所でもあり、山中峠、木の芽峠、栃ノ木峠、湯尾峠のいずれの山越えの道を選んでも今庄宿は避けて通れぬ場所であった。そのため、福井の初代藩主、結城秀康公は、北陸道を整備するにあたり、今庄を重要な宿駅として防御に配慮した街並みの整備を図った。こうして文化年間(1804年~1818年)には、北国街道に沿って南から北へ向かって、上町、観音町、仲町、古町、新町の五町が出来上がり、家屋が櫛の歯のように立て込みながら、街並みは1キロメートル以上に及んだという。江戸時代のある旅日記には、茶屋で田楽やそばが売られ、都なまりの言葉で呼び込みをする今庄宿のにぎやかな情景が記されている(「北国街道今庄宿」南越前町より)。宿場の中心部、仲町には、福井・加賀両藩の本陣や脇本陣、問屋、多くの造り酒屋や旅籠が立ち並び、天保年間(1830年~1844年)には今庄宿全体で戸数290余り、うち旅籠50軒、鳥屋15軒、茶屋15軒、酒屋15軒があったとされ、今も街並みには当時の宿場町の面影を感じ取ることができる。
このように、古くから峠越えの道がすべて集まる今庄は、北国の玄関口として交通の歴史とともに歩んできた。ただ、明治に入ると江戸時代の宿駅制が廃止され、さらに陸運の手段が人力車や荷車に変わり、明治21年(1888年)には新国道(国道8号線)が開通。今庄宿は徐々にその活気を失っていく。
こうした中、今年の5月21日、文化審議会は重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)として、この今庄宿を選定するよう萩生田光一文部科学相に答申した。江戸時代に宿場町として栄え、昔ながらの地割りや、重厚感のある町屋が立ち並ぶ歴史的な町並みが評価されたのである。対象となるのは今庄宿のほぼ全域の旧北国街道約1.1キロ区間、約9.2ヘクタール。エリア内には昭和30年代以前に建てられた「伝統的建造物」の対象が約160戸あり、そのうち景観の維持・復元について所有者の同意が得られた118戸が同建造物として登録されることになる。これにより、今庄に今も現存する「旅籠 若狭屋」、「脇本陣 京藤甚五郎家」、「社会教育の拠点 昭和館」などが、これまで以上に注目を集めることになるであろう。こうした事実は、10年以上前から町並み保存活動を続けてきた同地域にとって大変喜ばしいことでもあり、この重伝建の指定が新たな町おこしの起爆剤になることを大いに期待するところである。
コロナ禍で将来が危ぶまれる時代、ひょっとしてこれからの日本の再生は、こうした地方圏の足下にある資源の磨き上げにかかっているのかも知れない。「福井で学ぶ、福井でしか学べない経営学とは」
ご存じの通り福井県はモノづくりの盛んな土地であり、少し前のデータだが「平成28年(2016年)経済センサス基礎調査(速報)」によれば、「産業大分類別の従業者数と割合(民営)」において最も多いのが、「製造業」の83,059名(21.9%)となっている。本学においても、看護学科、社会福祉学科を除いた全ての学科(経済学科、経営学科、生物資源学科、海洋生物資源学科)において、製造業に就職する学生の比率が最も高くなっているのが現状である。そういった点からも、本学の学生がモノづくりについて学ぶことは、自分自身の進路を考えるうえでも、大いに役立つことであるといえよう。
一方で、私が所属する経済学部・経営学科というのは、経営学部や商学部なども含めて考えれば、全国の多くの大学に存在する学部・学科である。こうした、いわば「ありふれた学部・学科」である本学の経営学科を、受験生の志望先として選んでもらえるようにするためには、この大学でしか学べない経営学とは何かについて常に模索し、それを実践して他大学との差別化を図ることで競争力を高めていく必要があろう。そのために、多くの教員が趣向を凝らした教育実践を行っている。以下では、私が行っている取り組みについてご紹介する。
私は主に「生産管理論」という科目を担当し、モノづくり企業の経営に関する講義やゼミを行っているが、モノづくりは普通の学生にとって日頃あまり触れる機会が少ないことから、どのようにして関心を持ってもらえるようにするかが大きな課題であると感じている。一方で、文系学生がイメージを持ちにくい製造業にとっては、いかにして将来の会社を支えるマネジメント人材を確保していくのかが課題となっている状況にある。福井にはモノづくりを行う優良企業が多く存在するが、いわゆるBtoBビジネスが多いことから、学生への認知度が低いという課題を抱えている。経営学を学ぶ学生がモノづくりに関心を持ち、それについて学ぶことで経営学の面白さを感じてもらうとともに、そこで学んだことをモノづくり企業において活かすことが出来れば、学問と将来の進路の両面でプラスに働くことになるといえよう。ひいては地域の活性化にもつながることにもなるわけである。
私の担当する講義やゼミでは、モノづくりの現場を見たり、話を聞いたりということを積極的に行っている。講義においては、モノづくり企業からゲスト講師をお迎えして、その会社のモノづくりに関する講義をお願いしている。それまでの講義で学んだ内容が実際にはどのように行われているのかについて、実際の話をお伺いすることで理解が深まることから、学生には非常に好評である。また企業にとっては、学生に対して直接アピール出来ることや、講義を行うにあたり自社の取り組みを改めて見直す機会になると、良い評価を頂いている。
また担当する演習(ゼミ)においても、テキストを用いた勉強に加えて、福井の企業にご協力頂いて、実際の製造現場を見学してその空気を感じることも積極的に行っている。高いシェアを持ち日本全国あるいは世界中で多くのユーザーに利用されている製品が、ここ福井の地で製造・出荷されている様子を目の前で見ることで、見学した学生には刺激になっているようである。さらに卒業研究(卒業論文)においては、企業への実態調査を課しており、企業へのアポイントやヒアリング調査などを学生自身が行うことで、「生の声」を踏まえた卒業研究に取り組んでいる。
いずれも非常に重要なことは、単なる企業のアピールということではなく、この取り組みはあくまで教育の一環であり、そのことを講師や企業の方がご理解されているという点である。ゲスト講義においては、事前に教育目標やゲスト講義の位置づけをお伝えし、当日の講義内容について入念に打ち合わせを行ったうえで、これを実施している。見学においても同様に、教育目標や見学の位置づけをお伝えし、事前の打ち合わせと下見を行ったうえで(安全にも十分に配慮したうえで)実施している。そして講義や見学終了後に学生のリアクションもお渡しして、学生の理解度をお伝えしている。
いずれも講師や企業には大きなご負担をおかけするため心苦しいところではあるが、きちんと趣旨を理解し非常に前向きにとらえてくださり、積極的に取り組んで頂いていることから、結果として学生にも非常に好評な取り組みとなっている。当然、教員にも大変な手間がかかるわけだが、それ以上の大きな教育効果が得られていることを実感しており、「実際に見て、感じて、楽しんで学ぶ経営学」につながっているのではないかと考えている。
福井には、モノづくりの経営学を学ぶうえで「最高の教材」といえる企業が多く存在し、また企業と大学とが近い関係にあることから、モノづくりをより身近に学ぶことが可能となっている。そして、大企業の事例が取り上げられることが多いこれまでの経営学とは異なり、地方都市である福井で学ぶ、福井でしか学べない経営学を学ぶことが出来る点も重要であろう。これによって、教科書的な経営学を相対化して分析・考察するとともに、実態に触れながら学ぶことで、経営学をより深く学ぶことにつながるといえる。
さらに、こうした企業に本学の卒業生がお世話になっていることも多いため、講義や見学において自分の仕事内容などもお話してもらうことで、学生が職業意識を身につけることにつながるとともに、大学時代の勉強が仕事にどのように関連しているのか、あるいは大学時代にどんな勉強や経験をしておくべきか、といったことも考えることにもつながっている。そして、これまであまり身近ではなかったモノづくりの世界で、自分の先輩が頑張っている姿を見ることで、先輩が「橋渡し役」となって将来の進路として意識することにもなろう。
言うまでもないことだが、大学は単に就職を有利にするための「就職予備校」ではなく、あくまで学問を行う機関であり、その方針から絶対に外れるべきではないと私は考える。但し、そうはいってもやはり就職は学生にとって重要であり、就職への意識がきっかけとなり学問への関心が高まり、熱心に学問に取り組むことで結果として将来の進路につながることは、学生にとっては悪いことではないとも考えている。その両者のバランスが重要なのであろう。
福井にはこうした点を理解し、前向きに協力してくださる企業が多いことも、この取り組みを行ううえで大変有り難いことである。この場を借りてこれまでご協力くださった方々にお礼を申し上げるとともに、今後も「福井で学ぶ、福井でしか学べない経営学」を続けるために、引き続き地元企業の方々のご協力をお願いする次第である。以上
日中間関係からみた中国の人口減少の含意
中国の人口が減少しているのではないか。そんな話題が今月、いくつかのメディアによって報じられました。1年以上にも亘るコロナ禍で疲弊しきっている日本の私たちには、あまり響かないニュースだったかもしれませんが、実はこれからの日中関係を考えるうえで重要な啓示となるかもしれません。
きっかけは、中国統計局が先般公表した、2020年人口センサスの結果速報です。日本経済新聞の国際部の方から電話取材が入りました。コロナ禍の影響は?今後中国の人口は?などなど1時間近くに亘る質疑応答の結果は、5月12日(水曜日)の朝刊に掲載されていますのでご興味のある方はご覧ください。
中国に限らず、人口減少が長期化する要因は低迷状態が続く出生率です。長期的な人口減少に入ってしまった国は今のところ日本だけです。次は韓国や台湾か、とみられていましたが、人口大国・中国が日本に続くとなると国際的なインパクトも大きいのではないでしょうか。他方、“国民すべてのお腹を満たす”ために計画生育のもと人口爆発の抑止を目指してきた戦後の中国にとっては、人口減少は大いなる成果でもあります。とは言え、低すぎる出生率、少なすぎる新生児数は想定外であったと思います。近年では計画生育の条件を徐々に緩和し、ついには“一人っ子”政策を事実上撤回したのにもかかわらず、出生数が増える兆候はまったくありません。当然、中国国内でも真摯な議論が続いています。
規制を撤廃したのにもかかわらず少子化に歯止めがかからない最大の要因は、急速に進む経済成長と生活水準の劇的な向上にあるとみられています。GDPでは2010年に、それまでアメリカに次ぐ2位の座を日本から奪取し、今では日本の3倍近い規模になっています。人口一人あたりのGDPではまだ、日中間に大きな開きがありますが、その差は急速に縮まっています。1990年の前後でしたが、私は中国の天津に交換留学生として1年半近く住んでいました。当時の天津での生活費は住居費・食費等を含めて年間30万円ほどで、日本の国立大学の1年間の学費とほぼ同額。お金のことはあまり気にせず中国を体感することができました。今ではどうでしょう。2000年頃までは、中国との共同研究などで必要となる諸経費は日本側が負担することが多かったように感じますが、近年では逆に中国がすべての費用を負担してくれます。今年始めにリモート会議に招聘された際は、30分ほどの参加にもかかわらず10万円相当のアメリカドルによる謝金を提示されました(現職が国家公務員であることもあり残念ながら辞退しましたが・・・)。
今日、日本に長期に在留する外国人約300万人のうち30%弱が中国国籍の方々です。リーマンショックや東日本大震災を経て紆余曲折はあるものの、コロナ前までは概ね増加傾向にありました。2013年頃から急増しているベトナム在留者の在留資格の約半数が「技能実習」であるのに対し、中国の在留者の場合は約40%が「永住者」です。日本に長期滞在している理由は多様であること示唆しています。最近では、海外で多くの死者が出るような事件・災害が多く報道される一方、国内では魅力的なイベントが多く企画・実演されるなど、海外、特に発展途上地域にわざわざ足を運ぶ機会は減っています。何でもリモートで疑似体験できることになったこともあるでしょう。この間に世界は、私たちの古い思い込みを凌駕して“豊か”になり、停滞する日本との格差はいつの間にか相当縮まっています。経済格差を誘因として海外から日本に外国人労働者を誘致することは早晩難しくなりそうです。経済力以外の日本の“魅力”とは何なのか、海外に行けない今だからこそ、落ち着いて考えてみる必要があるのではないでしょうか。
3月に参画した中国との共同研究会の席で、中国側の代表者の方が挨拶されました。“今年東京オリンピックが無事開催されることを祈念いたします。そして、北京において来年2月に開催される冬季オリンピックにも是非お越し下さい!”地域産業の高度化を目指して
福井県の産業構造を眺めてみると、その特徴は、製造業と建設業に特化した地域であることと、その中で、製造業は、繊維産業や眼鏡枠産業、伝統的工芸品産業などを中心に多様な産業で付加価値生産性が低いといった特徴がある。そのため、福井県の産業界では、これまで各産業の高付加価値化を目指して、技術・製品開発、流通の簡素化、販路開拓など多様な試みを実践してきたことは言うに及ばない。
話は変わるが、フランスの経済学者・思想家のジャック・アタリは、2009年の著書「危機とサバイバル」の中でパンデミックの発生を予測し、今回の新型コロナウイルス感染症が、1929年の世界恐慌、2008年のリーマンショックよりも甚大な被害を及ぼすことを示した。そして、これを回避するために、世界の経済を全く新しい方向に設定しなおす必要性があることを述べている。具体的には、世界は爆弾や武器ではなく医療機器や病院、住宅、水、良質な食糧などの生産を長期的に行うべきであり、そのためには多くの産業で大規模な転換が求められることを示唆している。すなわち、人類が生きるために必要な食糧、医療、教育、文化、情報、イノベーションなどの提供を意識した産業、生きるために本当に必要なものの生産に集中することこそが今求められているということであろう。
ちなみに、コロナ禍における地域産業の生産活動に着目すると、例えば、福井県立大学が年末に実施した企業調査(福井県企業の「コロナ禍での事業活動に関する緊急調査」)では、アンケートに回答した企業521社の約2割の企業でウイルスや自然災害などから身を守る新製品・サービスの開発が行われていることがわかった。それは、まさに地域企業の間で「命を守る産業分野」への挑戦が始まったということではないだろうか。「命を守る産業分野」とは、今回のコロナ感染症だけでなく自然災害など人間に危険を及ぼす現象の発生を予測し、間接、直接的に人の身体を守る製品開発・サービス開発を行う分野を指す。例えば、農産物・食品加工分野でいえばクオリティーの高い作物や食品加工物の生産、製造業の分野ではウイルスをシャットアウトする住宅部材の生産や身を守るフェイスシールド、防護服・マスクなどの生産、医療行為、ドローンを使った監視システムなどの研究・開発を行う産業分野を指す。それは、繊維産業や眼鏡枠産業、化学産業といった多様な既存産業の垣根を超えた産業横断的な分野でもある。
ところで、日本の場合、研究開発企業の割合は全体の8~10%程度といわれる。その中で、今回の企業調査でわかった2割にも及ぶ新製品・新サービス開発企業の割合は、非常に高いウエイトと言わざるを得ない。地域産業の歴史を振り返ると、例えば、繊維産業では、明治以降、シルクライク、ウールライクといった考え方をベースに天然繊維から化合繊織物の転換が進み、この地に合繊繊維を中心とした織物産地を誕生させた。眼鏡枠産業でも、真鍮(しんちゅう)→金・銀・銅・セルロイド→洋白・ハイニッケル→チタン・NT合金・マグネシウム亜鉛からマグネシウムまで素材の加工技術の開発が産地の発展を支えた。また、近年の地域中小製造業の技術力の高さは言うに及ばない。こうした中で、今回発生したコロナウイルス感染症は、ここで述べた地域製造業の産業特性、持ち前の開発力に火をつけたような気がする。
ならば、地域はこの「命を守る産業分野」を地域の新たな産業分野と位置づけ、育成することも必要ではないか。具体的には、「命を守る産業分野」参入に向けて頑張る企業へのものづくり・技術の高度化支援や、そのための金融支援、新製品・技術開発・サービス開発にまつわる情報提供・相談業務のさらなる充実が必要であり、合わせて昨今のデジタル化に向けた企業行動にも着目した支援も必要と考えられる。
その結果、地域産業の高付加価値化、労働生産性の向上を促し、最終的には産業構造の転換・高度化にもつながることを期待したい。「自由な貿易」から「公正な貿易」へ
コロナ後の世界経済は、ワシントンコンセンサスによるグローバリゼーションが推進される中で顕在化した「富の偏在」や「格差の拡大」の是正に向けた制度改革とともに、「自由な貿易」から「公正な貿易」へとパラダイムシフトが進む可能性がある。
そう思う理由は、いくつかある。まず、世界経済全体で見た所得再分配上の不平等があまりにも拡大している点だ。1980年と2016年の世界の家計所得の伸びを比較した調査によると、この間に増加した世界のトップ1%の所得は下位50%の2倍以上に及ぶ。また、別の調査によれば、世界でもっとも裕福な8人が保有する資産は、下位半分が保有する資産とほぼ同じだ。そして、そのうち6人が暮らす米国では、240万人に当たるトップ1%の富裕層が、数ではその50倍の労働者階級全体の倍の所得を手にするに至っている。最後の米国での調査においては、過去40年間で両グループへの富の配分は逆転したことも示されている。しかも、この間、労働者の実質賃金は殆ど変わっていないのだ。こうした事実は、自由化や規制緩和、さらには、富裕層や大企業への減税によって、富める者が富めば、いずれ、貧しい者にも富が浸透する、とした「トリクルダウン効果」はいつまで待っても現れないことを如実に示すこととなり、かつてないほどに人々の間に不平等感が募っているのである。
格差は国家間レベルでも広がっている。経済理論上は、自由貿易は競争力が弱い国においても、その国の中で比較優位性の高い分野に特化することで、社会的余剰(豊かさ)を増やすことができる、はずであった。しかし、現実には、グローバリゼーションの結果、急速に経済発展したのは、中国やASEANなどごく一部の新興・途上国に過ぎない。それは、貿易のメリットを途上国にもたらすには、市場アクセスだけでは不十分なためである。たとえば、EUでは、後発途上国(LDC)に対して、武器以外のすべての製品の輸入関税を免除する優遇制度(EBA)を採用しているが、EBA対象国であるタンザニアからEUへの輸出は増えていない。これは、後発途上国の輸出機会を活かすには、外資の導入などを通じた、生産能力の拡大や技術支援が必要なためである。この点において、アフリカにおける中国の一帯一路構想は、一定程度評価できる。しかし、「債務の罠」の問題を抜きにしても、アフリカへの援助に際して政治的な制約を課さない中国の姿勢には、アフリカ側に好意的な印象を与える一方で、アフリカ域内の汚職や人権侵害などを助長する恐れがあるとして危惧する声が上がっているのも事実である。
また、昨年、『ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)』に掲載された論文によると、環境に与える「富」の影響が深刻なレベルに達している。これまで、環境にもっとも大きな影響を与える要因は「消費」と「技術」だと考えられてきたが、ここ数十年で、豊かな国の消費者による「消費」が急拡大した結果、技術革新を通じて削減できるレベルを遥かに超えてしまったのである。つまり、地球上の生活に関連した温室効果ガス排出量の10%を約40億人の「世界における収入下位50%」が生み出しているのに対して、その100分の1に過ぎない4000万人の「世界でもっとも裕福な0.54%」が生み出す同排出量は14%に達しているのだ。さらに、先進国に住む多くの人が含まれる世界のトップ10%の富裕層は環境への影響のうち25~43%の責任を負っている。
ところで、不思議なのは、際限のない「富」への執着が社会的問題を引き起こしている、という点である。なぜなら、ある一定以上の水準を超えると、所得の伸びは幸福度の高まりに寄与しなくなる、とした「イースタリンのパラドックス」が示唆するように、これまで「富」への執着は所得の増加とともに薄れていくものと思われていたからである。しかし、今、現実の世界で起こっているのは「地位消費」(positional consumption)という概念による正反対のメカニズムである。即ち、人は基本的な欲求を満たすと、社会的希少性によって少数の人しか入手できない「地位財」(positional good)を求めだすというのだ。そう考えると、米ベンチャー企業が2022年に開業予定の「宇宙ホテル」への滞在料金が、12日間で10億円であるにもかかわらず、すでに、4か月先の予約まで完売というのも決して不思議ではない。しかし、今後、先進国の人々が一斉に地位財を求めだすと、地球環境の破壊はとめどなく加速していくことが懸念される。そのため、「もっとも裕福な人々に課税すること」や「弱いエコシステムと貧しい人々に投資すること」が必要とする同論文の主張は、ロールズの「正義」の概念とも合致しており、検討に値する。
次に、国際貿易に関して問題と思われるのは、アフリカにおける中国の「一帯一路」にみられるように、新興・途上国の中には、欧米先進国とは異なる価値観や慣習によって、開発や貿易を通じて人権侵害や環境破壊が行われている可能性があることだ。現行の国際ルールでは、たとえ、コスト削減のために人権侵害や環境汚染に加担しているとしても、それに対してペナルティを科すのは難しい。しかし、グローバリゼーションの制度的欠陥が鮮明となった今、世界経済秩序に関する新たな制度設計の構築が必要となっている。具体的には、「自由な貿易」から「公正な貿易」への変更・修正である。 では、「公正な貿易」とは何か。ダンピング関税を例に取ると、これまでは、結果としての価格の正当性がチェックされてきた。たとえば、中国のWTO加盟時に、貿易相手国は最長15年間、中国を「非市場経済」として扱うことが認められた。それによって、輸入国は中国からの輸入品に対して反ダンピング税を課すことが容易になった。コストの割高な国の生産費用を中国における生産費用として代用することができるためだ。現在、中国がすでにWTO加盟後15年を超えたことで、多くの国は中国に市場経済としての地位を与えているものの、米国とEU、そして日本は未だに認めていない。ただ、「市場経済」としての承認の遅れは、単に、貿易(覇権)戦争の悪化を招くだけとの指摘がある。そこで、これから目指す「公正な貿易」では、これまでのような、結果としての価格の正当性というよりも、そこに至る経緯が重要となってくる。換言すれば、「ソーシャルダンピング」や「エコロジカルダンピング」の概念を、国際的な貿易ルールの中に反映させるべき、ということである。実際、現在協議中の、中国とEUとの投資協定では、中国の人権問題も俎上に上がっている。また、EUは温暖化対策が不十分な国からの輸入品に価格を上乗せする「国際炭素税」を2023年までに導入する方針を打ち出している。こうした政策は輸入価格の上昇につながることから、消費者余剰(消費者の利益)を減らすとして反対意見が出ることが予想される。けれども、我々がほんの少し我慢することで、国際間の不平等や環境破壊が抑制され、世界全体の総余剰(万人の利益や満足感)は増えるのである。ならば、我慢した分だけ幸せを分かち合えると考え方を改めてはどうか。 以上人の幸せを測る国際標準とは?
“0段目はあなたにとって「最低の生活」、10段目はあなたにとって「最高の生活」。あなたの生活は今、ハシゴのどの段階にいますか?”読者の皆様はこの質問に0-10のどの数字を選ぶだろうか。ぜひ一度、ご自身の中で回答してもらえればとおもう。
この質問は、人の幸せを測る現在の国際標準であり、キャントリルの階梯と呼ばれる方法だ。人生をハシゴと見立て、主観的な幸福度や満足度を測定する際に世界中で最も活用されている。例えば、国連機関が実施している世界幸福度調査(World Happiness Report)の世界ランキングも、この測定方法の結果に基づき公表され、マスコミを通じてそのランキングは注目の的となっている。最新の2020年の結果では、日本は153国中62位と低迷し、北欧諸国が上位を占めている。
当然ながら上位国の常連である北欧諸国から学ぶことは多く、また日本は「寛容度」や「人生における選択の自由度」など、改善しなくてはいけない課題があることに論を待たない。しかし同時に、人生をハシゴと見立て、上にあがればあがるほど幸せであるという考え方・測定方法は本当に国際標準として普遍的なものであるのか、ということには議論の余地が多分にある。
私自身はブータン王国で人の幸せを測るGNH調査にご一緒させてもらったが、その時に実感したことがある。ブータンのように中庸の文化を持つ国において、ハシゴにおける9や10を回答する者の割合は少ない。真ん中に位置する5を基準にしながら、よい状態と感じていれば、6や7を選ぶ傾向がある。2015年のブータンの調査では、この国際標準の質問での回答の平均値は6.88だった。また、調査において日常に感じている感情を尋ねる質問もあるが、ブータン人が感じてる一番多いポジティブな感情は「おもいやり(Compassion)」であった。刺激の強い高覚醒の幸せというよりも、平穏や安寧という言葉が似合う幸せの存在をブータンからは感じた。上にあがればあがるほどいいという価値観が幸せの唯一の源泉ではなく、文化的に必ずしも当てはまらない国も多いということを認識する必要がある。
そこで現在、日本の公益財団法⼈であるWell-being for Planet Earthを中心に、西洋の価値観だけでなく日本を含む多様な地域の価値観も尊重し、新しい国際基準となる幸せ(ウェルビーイング)の測定方法の検討を進めている。様々なテーマでの議論が続いているが、一番注目したいのが、人生の調和・ハーモニーやバランスがとれているという幸福感を測定することへの挑戦だ。現在の幸せ測定の国際標準をハシゴ型と捉えるのであれば、振り子型の調和やバランスを重視した測定方法と言える。
幸福度の議論はどうしても結果としてのランキングにのみ視線があつまってしまうが、ぜひ何をどのように測っているかにも一緒に注目してもらえれば嬉しい。福井県の在宅医療・介護と地域包括ケアシステム
わが国は、住み慣れた地域で自分らしい生活を維持・継続するために地域包括ケアシステムを推進している。福井県でも、在宅医療・介護を必要とする住民が安心して地域で療養生活を継続することができるよう、地域包括ケアシステムにおける在宅医療・介護連携をシステム化している。本コラムでは、「在宅医療・介護連携に関する市民アンケート調査」(大久保清子、2019年11月)結果の一部を紹介し、自宅で楽しく豊かな療養生活を送るために必要なポイントをお伝えしたい。
本調査は、2019年11月時点で福井県内に居住する市民約2,400名で、居住地や性別、年代(20~80歳代)を無作為に抽出した。回収1964部、回収率は82%である。男性22.4%、女性77.2%、不明0.4%で、40歳代が21.3%と最も多く、次が30歳代、50歳代の20.3%である。家族構成は、2世代世帯(子ども)33.7%、3世代世帯21.9%、夫婦のみ世帯15.6%、2世代世帯(親)13.6%、単身世帯12.1%であった。
回答者が感じている「自宅で療養するときの不安」は、「精神的な負担」が79.0%と最も多く、次に「経済的な負担」70.8%、「仕事と介護の両立」48.9%であった。医療や介護に関する身近な相談相手で最も多いのが「家族」88.8%で、次に「友人・知人」40.1%であった。在宅医療を実現できない・希望しない理由で最も多かったのは、「介護する家族に負担がかかる」83.3%であった。しかし、人生の最期を迎えたい場所は「自宅」が48.4%と最も多く、次が「ホスピスなどの緩和ケア施設」23.0%であった。在宅医療の認知度で見ると、在宅医療を良く知っている人の方が自宅で最期を迎えたいと考える割合が高く、余命で大事にしたいことは、「家族や友人のそばにいること」71.2%、「家族の負担にならないこと」67.0%、「痛みや苦しみがないこと」61・0%であった。
この結果をみると、県民は家族や友人をとても大事にしており、最期まで家族や友人とかかわりながら自宅で療養生活を送りたいと思っているようである。しかし、家族に負担をかけない、痛みや苦しみを軽減するため施設に入所しようと考えていると思われる。在宅医療は、訪問看護や介護などの多職種や近隣住民とも連携し、その人・その家族らしい療養生活を支えていくものである。在宅医療を良く知っている人が自宅で最期を迎えたいと考える割合が高いのは、それができることを知っているからであろう。自宅で医療や看護・介護を必要とする方は、自分一人ですべてを抱え込むのではなく、日常的なケアは在宅医療や看護・介護の専門職に任せ、家族や友人が楽しく過ごすための豊かな時間と空間をつくってみてはどうだろう。その実現に向け、近隣の訪問診療や訪問看護・介護事業所、地域包括支援センター等に相談し、福井県の多職種連携システムを活用して欲しい。福井県の幸福度再考
一般財団法人日本総合研究所が発表している「全47都道府県幸福度ランキング」で、福井県は2020年も総合1位に輝いた。同ランキングは2014年から隔年で実施されており、福井県は開始以来、4連続で総合1位の座を守り続けている。同時に、ランキングの算出方法に関して、次回からは統計指標に依拠したものから、幸福度に関する住民の行動や実感を重視する方向に変更することも明らかにされた。この変更で福井県の順位がどのように変化することになるのか、期待と不安が交差するところである。
振り返ってみれば、統計指標から客観的な基準で算出された幸福度や暮らしやすさに関して、福井県は無類の強さを誇ってきた。経済企画庁が1994年から1999年まで公表していた「新国民生活指標」(「豊かさ指標」、「暮らしやすさ指標」などとも呼ばれた)でも、福井県は6年連続で第1位に輝いている。貨幣的な指標では捉えきれない生活の「豊かさ」を、「住む」、「費やす」、「働く」、「育てる」、「癒す」、「遊ぶ」、「学ぶ」、「交わる」の8つの指標から測定したランキングである。2011年に刊行され話題になった『日本でいちばん幸せな県民』(幸福度指数研究会、PHP研究所)でも、総合ランキング1位はやはり福井県であった。都道府県レベルのランキングではないが、東洋経済が刊行している『都市データパック』では、800近くある日本の市の「住みよさランキング」が公表されている。算出に大型小売店店舗面積といった指標が使われているため、郊外に大型ショッピングセンターがオープンすると順位がジャンプアップしたりすることもあり、変動の目まぐるしいランキングなのだが、福井市、坂井市、鯖江市あたりはベスト20の常連になっている。
いずれも統計指標から客観的な基準で算出されたランキングではあるが、算出の主体によって使われる指標や計算方法は少しずつ異なっている。指標の数値そのものも年次変動を繰り返している。言い換えれば、その程度の違いであれば、ものともしない抜群の強さを福井県は示してきているのである。中央省庁のキャリア官僚、大学の研究者、シンクタンクの研究員とそれなりの知的能力を備えているはずの人たちが算出した数字が、どれもこれもまったくの的外れということも考えにくいだろう。
一方で、こうした数字上の強さに県民の実感が伴っていないという声も少なくない。福井県が地上の楽園というわけではなく、すべての県民があらゆる局面で幸せに満ち満ちた日常生活を送っているなどということはあり得ない。多くの県民がさまざま不満や生きがたさを抱えていても当然だろう。ただ、それにしても、数字上の幸福度の高さと生活実感のギャップを指摘する声を耳にする機会が多いように感じている。以下では、その理由についていくつかの観点から検討してみたい。
個人的には、田舎コンプレックスが幸福度の高さを素直に受け入れられなくしているような気がしてならない。今でこそ福井県の数字上の強さに誰も驚かなくなっているが、1994年の経済企画庁の発表は、この手のランキングの嚆矢ということもあり、かなりの意外性をもって受け止められたことを記憶している。福井県が1位に選ばれただけでなく、東京を除く首都圏の地域が軒並み下位に沈んだことも、その一因となっていたようだ。福井県が1位をキープし続けた6年間、最下位に沈み続けたのは埼玉県であった。「新国民生活指標」の妥当性そのものが、議論の的になることも少なくなかった。ニュース・ステーション(当時人気の高かった報道番組)でもそのあたりが取り上げられ、「遊ぶ」の項目に「人口当たりのパチンコ店数」が使用されていることに触れ、キャスターの久米宏氏が「パチンコ屋の数が多いと暮らしやすいんでしょうか」と例の皮肉たっぷりの口調で批判していたのを憶えている。この時点では自分が福井県で暮らすことになるとは夢にも思っていなかったのだが、滋賀県の小さな町で暮らす田舎者の一人として、「暮らしやすさで田舎の後塵を拝するのが、都会の住民にはこんなにも受け入れがたいのか」と驚き呆れたことを鮮明に記憶している。「福井のような田舎が日本で一番、幸福で住みやすいはずがない」という先入観は、都会に対する劣等感とあいまって、福井県民の間にも多かれ少なかれ共有されているのではないだろうか。奥ゆかしさは福井の県民性の美質の一つだとは思うが、住みやすさに関しては夜郎自大にならない程度にもう少し自信をもってもいいような気がしている。
次に、これは以前のコラムでも触れた論点だが、福井県民が福井県の暮らしやすさに気づきにくいという側面もあるだろう。福井県は定住性が高く、県民の多くは福井県外で暮らした経験に乏しい。このことが、他府県と比べて福井がどうなのかに関して、具体的にイメージすることを難しくしている。例えば、通勤時間の短さに幸せを感じている福井県民がどれほどいるだろう。マイカーを利用してドア・トゥー・ドアで片道30分以内という通勤スタイルは(SDGsという観点からは問題含みかもしれないが)、首都圏のベッドタウンの住民からは垂涎ものだと思うが、その恩恵はほとんど意識されていなのではないだろうか。満員電車で片道1時間半近くすし詰め状態を余儀なくされるという経験がないのだから、気づきようがないのかもしれないが、まさに雲泥の差である。1日につき2時間程度の差なので、年に250日通勤するとして、20年間その生活を続けると、合計で10000時間ほどの違いになる。ざっと計算で400日以上に相当し、1年を軽く超える差になる。20年につき1年あまりの可処分時間の差は見過ごすには大きすぎる気がするが、定住性の高さゆえに福井県民の意識には上りにくい。子育てのしやすさにしても、その実感が薄すぎるような気がしてならない。筆者は関西から福井県に移り住み、福井県で子育てをした人間だが、県内でベビーカーを押していて嫌な顔をされた経験が本当に「ただの一度もない」。このことがどれほど特筆に値するかは、福井県でそれを当たり前のこととして享受し続けてきた人には実感できないだろう。子どもたちの通学時の交通安全の立ち番やボランティアの方々の姿が、地域に見守られて育っているという安心感をどれほど育んでいるのかも、福井県ネイティブには当たり前すぎてピンとこないのではと思う。当たり前のことは当たり前すぎて、そのありがたみを実感しにくいものなのだ。
福井県民が幸福度を実感しにくい理由としてよくあげられるものに、多様な価値観や生き方に対する不寛容や人間関係のしがらみの強さなどがある。こうした課題を克服していくことの重要性を過小評価するわけではないが、その前提として確認しておくべきことがあるような気がする。筆者は、福井県の暮らしやすさを支えている大きな要因として、家族間のつながりや地域の人間関係のネットワークの緊密さがあると考えている。血縁(産む生まれる)や地縁(同じ地域に住み合わせる)といった結びつきは、運命的で変更が容易でないことを特徴としている。こうした選択性の低い関係を基盤とする結びつきをソーシャルキャピタル論では結束型と呼んでいる。これに対して、サークルやクラブへの加入、ボランティア活動への参加のような興味や関心の共有に基づく選択性の高い結びつきは架橋型と呼ばれる。福井県の強みは結束型の結びつきの緊密さにあると考えるのだが、こうした結びつきには匿名性の低さや同調圧力の強さといったダークサイドも付きまとう。これとは裏表の関係になるのだが、多様な価値観や生き方に対する寛容さは他者への無関心と紙一重でもある。近代的な価値のチャンピオンである自由と平等に関して、完全に両立させることは原理的に不可能であることが知られている。完璧に自由でかつ完璧に平等な社会は望んでも不可能であり、両者のバランスに関するコンセンサスをどのように形成するのか、そのバランスをどのように実現するのか、が現実の課題となる。幸福度の実感をどうやって高めていくかに関しても、「あれもこれも」の完璧な両立はないものねだりで、コンセンサスやバランスの問題であるといった認識が適切なのではと考える。結束型のつながりにも、架橋型のつながりにも、それぞれ一長一短があり、それを踏まえたうえで、さらに2つのつながりをどう醸成し、どうバランスさせていくのか、といったかなり込み入ったチャレンジが必要とされる。ただ、容易ではないということに必要以上に悲観的になることもないだろう。血縁的な結びつきに関して、福井県民が創出してきた三世代近居というライフスタイルは絶妙なバランスのとり方だと考えている。
田舎コンプレックスを払拭し、すでに備わっている暮らしやすさを再確認しつつ、新しい局面を切り開いていくことは、困難ではあるが十分にやりがいのあるチャレンジだろう。「コロナ禍の人口、コロナ後の日本」
コロナ禍のもとで人口動態が激変しています。
日本全体における出生数は、近年の減少傾向がコロナ禍においても継続しています。今年に入って登録される出生届は昨年の妊娠によって生まれてくる赤ちゃんがほとんどなので、コロナの影響がダイレクトに出生数に反映されるわけではありませんが、昨年の婚姻件数が多かったことからすると今年の出生数はもう少し多くなってもおかしくはありません。ちなみに、昨年の婚姻件数が多かった要因は“令和婚”によるものです。それでは、コロナ禍が出生動向にまったく影響を及ぼさないかいうと、そうとも言えません。今年5月以降の婚姻件数は一昨年と比べても大幅に減っており、来年以降の出生に少なからず影響を及ぼすことでしょう。加えて、市区町村によっては今春以降の妊娠届が減っているという報告がされています。他方で、死亡数は従来予測に反しあまり増えていません。そもそも人口の高齢化はコロナ禍でも確実に進行しているので、死亡率がこれまでと同じであれば死亡数は増えていくのが必然です。さらに、志村けんさんや岡江久美子さん(ご主人は福井県出身の大和田獏さんでしたね)などの著名人をはじめ新型コロナ感染が直接死因である累計死亡者数、ならびに女性の自殺者数の増加等の報道を目の当たりにしているので、今年に入ってからの死亡数が増えているような錯覚に陥っても不思議ではありません。しかしながら実際には、インフルエンザによる死亡者数が大幅に減少していることもあり、昨年末以降の死亡総数は推計を大きく下回っています。その結果、出生数を死亡数が上回ることで生じる人口の自然減の規模もかなり抑えられた状態になっています。それだけに、来年以降の揺り返しが危惧されることころです。
日本全体の人口動向を観測するには、さらに国際人口移動についても言及しないといけないのですが、当コラムの紙幅を考慮し、別の機会に詳しくお話しできればと思います。
最後に、コロナ後における地域人口の動向についても解説いたします。総務省統計局は今年の6月以降、コロナ禍における人口の地域間移動の状況を「住民基本台帳人口移動報告」を通じて詳報しています(http://www.stat.go.jp/data/idou/index.html)。東京都への転入者数から東京都からの転出者数を引いた転入超過数は、前年同月比でマイナスとなっています。人口の東京一極集中が小休止した状態です。東京都における転入超過数の減少は過去にも何度かみられます。直近では、リーマンショック後に大幅な減少が観測されています。逆に、福井県をはじめとする多くの県では、転出超過には変わりないものの、その規模は月ごとに縮小しています。
コロナ禍における地域間人口移動はこれまでと様相が明らかに違うのですが、それでは今後どうなるのかと問われると答えに窮するところです。拙速に私見を申し上げると、有効なワクチンが開発されるなどをきっかけとしてコロナ禍が早期に終息する場合、概ね元の人口動態に戻ると思われます。もちろん、緊急事態宣言の発令を機に突貫工事的に始まったテレワークやリモート会議や遠隔授業などは修正を加えながら定着していくとは思われますが(世界の潮流からは相当遅れた感はありますが・・・)、東京への人口集中や婚姻、出生の動向はさほど変わらないでしょう。なぜなら、今回のコロナ禍が、少なくとも日本においては多くの人びとの価値観を変えるほどには未だ影響を及ぼしていないようにみえるからです。もし今コロナ禍が去れば、Go To キャンペーンで堰を切ったように人びとは活動を再開し、電車や飛行機の混雑具合も概ね戻り、東京オリンピックもいろいろ変更はあるでしょうが何とか開催できそうです。“コロナ”は過去出来事として、“鬼滅”と並んで令和2年の流行語大賞となるでしょう。一方、コロナ禍が長期化した場合の経済的ダメージは計り知れず、給付金や補助金といった形で行われてきたこれまでの緊急避難的な公的支援では、現在の膠着状態さえ保てなくなるでしょう。今回のコロナ禍がどのような終結を迎えるのかにかかわらず、私たちには今すぐ始めなければいけないことがあると考えています。今後重ねて到来することが予想されるその他の災禍についても直視することから逃げず、将来世代に継承する価値のある“新しい日常”観のようなものを私たち一人一人が真摯に考え、コロナ後には地道に実装を進める準備をしておくことです。人と人との繋がりを大切にすることも大切だと思います。NHK連続テレビ小説「エール」の最終回で主人公・古山裕一もそう言っていたような気がします。コロナ禍における地域企業の状況から、企業経営の今後の方向性を探る
今般、福井県立大学では、コロナ禍における地域企業の状況と今後の地域企業のあるべき姿、方向性を探るべく、福井県内3,000社の企業に郵送によるアンケートを実施し、1,100社余りの企業から回答を得て、その実態並びに今後の地域企業の方向性を考察することができた。
まず、コロナ禍での地域企業の経営状況についてみると、2020年上期(1月~6月)における業況は、県内の70.4%の企業が「悪くなった」と答えている。ただ、売上げ状況をみると、全体の約4分の1が5割以上減少している一方で、約4分1は変わらない或いは増加しており、回答企業は今回のコロナ禍でも底堅く持ちこたえた企業が多かったようだ。また、資金繰りについても、5割弱の企業で「資金調達なし」(26.5%)や「自己資金」(18.4%)で賄ったと答えており、底堅い地元企業の経営状況がうかがえた。こうした中、今後の事業継続については、「継続」すると答えた企業が93.6%を占め、「休業」、「廃業」、「売却」を考える企業はわずか1.4%と少ない。つまり、今後も主に既存事業を軸に事業展開を続ける企業が多いのではないか。さらに言えば、経営戦略上は多角化するにしても今のビジネスに関連する分野で、経営資源をじっくり見極めながら新事業を考えるインサイド・アウト型の企業が多いものと思われる。一方、今回の調査では、地元企業が考える今後の成長産業についても尋ねている。その回答結果をみると、AI、ロボット、ICTなどのデジタル系分野と自然災害や感染症から身を守る、いわゆる命を守る産業分野への期待が高いことがわかった。
こうした結果から、地域産業・企業の今後の方向性を検討すると、おおよそ5つの方向性が浮かび上がる。
まず、第1の方向性だが、それは“ニューノーマル”時代に向けた新たなビジネスモデルの構築、所謂、つながるビジネスを構築すること。今回の新型コロナウイルス感染症拡大により、インターネットを通じて物事を行う動きが進んだ。すなわち、医療、教育、スポーツ、消費活動など様々な分野で、ネット上に広がるバーチャルな空間でオンラインビジネスばかりが活況を呈する姿を確認できた。それは、まさに非接触型社会への移行を意味する。在宅勤務の浸透、通学からオンライン学習へ、店舗に足を運んだ買い物からオンラインショッピングへ、対面による会議からオンライン会議へ、オンライン飲み会、オンラインによるライブ配信やスポーツ観戦など、挙げればきりがない。このように、時代は着実にデジタル社会へと切り替わっている。今回の調査でも明らかなように、仕事や暮らしの面で一旦取り込まれた仕組みが元に戻ることはないであろう。したがって、地域の産業・企業は、従来型の社会を意識しつつ、こうしたニューノーマルの時代の中で支持を集める新しいビジネスモデルの構築を考えなければならない。
第2の方向性は、“命を守る”ビジネス活動を推進すること。今回のアンケート調査では、デジタル社会の到来を意識して、今後の成長産業にAI(人工知能)や運転支援・自動運転、ICTなどを挙げる例が多くみられた。その一方で、スマートアグリ・農業ICT、予防医学、感染防護用の機能性繊維、防災・災害時通信ネットワーク、クオリティーの高い食品(加工)など命に係わる分野を成長産業と指摘する声も多く聞かれた。すなわち、今後の成長産業として期待できる分野は、“命を守る”産業分野、人類が生きるために必要な食糧、医療、教育、文化、情報、イノベーションなど、生きるために本当に必要なものの生産に集中することが求められている。福井の産業で例を挙げれば、農産物・食品加工分野ではクオリティーの高い農産物や食品加工物の生産、製造業の分野ではウイルスをシャットアウトする住宅部材の生産や繊維産業では防護服などの繊維衣料の生産ということになろう。
第3の方向性は、顧客ニーズ創造型ビジネスの展開を志向すること。今回のコロナウイルス感染症の拡大で大きな打撃を受けた産業は、観光・レジャー、飲食・サービス業であった。しかし、これら産業はコロナ終息後どこまで需要が復活するのであろう。戻るとしてもかなりの時間を要することは間違いない。本アンケートでも、今後の成長産業として観光・ツーリズムを挙げた企業ウエイトは全体の12.5%にとどまっている。観光・飲食など幅広い意味でのサービス業の特徴は、生産と消費の同時性、すなわち客が来て初めて生産が始まること。これら産業が従来型の対面による活動、言い換えればアナログな活動に留まることは、もはや得策ではない。待ちのビジネスから攻めのビジネスへと転換するためにも、既存のビジネスモデルに一味付けて事業の柱を多様化する、所謂、ハイブリッド化することが必要ではないか。福井県唯一の温泉地あわら温泉旅館の中には、夕食や源泉、浴衣のセットを提供し、自宅で温泉旅館を味わえる新プランを開発、家庭に居ながら温泉旅館の雰囲気を味わってもらおうという戦略を打ち出した。いわば、温泉旅館のテイクアウトである。また、福井市にある文具店では、オンラインで店内の様子を見ながら買い物ができるバーチャルショップに切り替え反響を呼んでいる。既存のビジネスに新たな価値を付け多様化することは、新たな顧客ニーズを創造することにもつながっていく。今後は、そんなハイブリッド型のビジネスモデルが求められる時代ではなかろうか。
そして、第4の方向性は、これまで述べた3つの方向性のどれを選ぶにしても、それを可能とするために、自社のデジタル化を推進することが必要となろう。すなわち、企業内部での効率性をさらに高めるために、デジタルツールの活用による働き方改革を実践することである。
最後に、第5の方向性として、昨今の時代変革を一つ挙げ、そこから今後の地元産業・企業の在り方を考えよう。それは、Society5.0の時代を意識した事業領域への参入であろう。例えば、国土交通省が進めるスマートシティ構想。これは、情報通信技術など最先端技術を活用した暮らしやすい未来型の都市をつくろうというもの。自動車や街頭に設置されているセンサーなど、あらゆるモノをインターネットでつないで、より安全で便利なまちづくりを目指す。新型コロナ感染症をきっかけに、元々進んで来たSociety5.0の時代が一気に加速することが予想される。そこで、例えば、前述のスマートシティに関連して、ICT、AI、自動走行など、地域企業はここに新たなビジネスチャンスを見出すことはできないか。