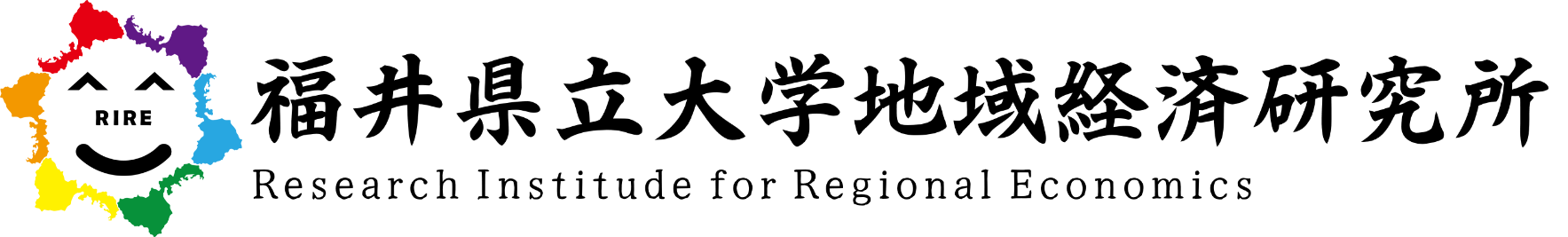2015年
地方創生政策に求められる「長期・総合的な検証と修正」
2015年末を迎えたので、筆者の研究領域である地域政策の分野で今年を振り返ってみることにしたい。さまざまな出来事があったが、「地方創生の本格的な取り組み」が1つの重要なトピックであろう。昨年末に国が「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定したのに続き、今年は多くの地方で、それぞれの人口ビジョンと総合戦略が策定された。
こうした一連の取り組みを「地方創生政策」と呼ぶとすれば、地方創生政策はその進展とともに、さまざまな点から議論されてきた。地方創生政策の意義として「地方消滅」という危機意識の醸成につながった点が挙げられたり、問題として国の主導や補助金依存など地方の自主性が不十分な点が挙げられたりしている。それぞれの議論に意味はあると思われるが、最も重要なのは地方創生政策が結果に結びつくのかどうかであろう。「終わりよければすべてよし」とは言い過ぎかもしれないが、結果が得られなければ「地方消滅」が待っているとすれば、結果を求めないわけにはいかない。
ところで、政策の「結果」がクローズアップされる契機となったのは、1990年代に普及した政策評価である。今では当たり前に言われるようになった「PDCAサイクル」も、政策評価の普及によるところが大きい。従来の政策は、計画(Plan)と実行(Do)の部分すなわち予算の編成と執行が重視され、その結果を検証(Check)して、より高い効果が望める形に修正(Action)する過程は必ずしも十分とは言えなかった。政策評価は、結果を重視することで新たな政策形成の枠組みをもたらしたのである。
政策評価が普及して四半世紀近くが経過し、政策の結果が問われるようになったことは、地方創生政策にも活かされている。一般的に政策評価では結果が客観的な数値で表されるが、地方創生政策でも5年後の基本目標やKPI(重要業績評価指標)の設定が求められている。また、行政活動の結果として住民にもたらされた便益(アウトカム)を把握するために、施策ごとの進捗状況を検証するための指標が重視される点も共通している。PDCAサイクルの実施も地方創生政策に明記された。政策評価の普及・定着が地方創生政策推進の基盤になっていると言っても良いだろう。
しかし、地方創生政策には政策評価の枠組みを超える部分があり、それがきわめて重要である。本題に掲げた「長期・総合的な検証と修正」である。
一般的に、政策評価では個々の事務事業について単年度もしくは5年程度(総合計画等の期間)の期間で結果が検証され、政策が修正される。地方創生政策でも個々の政策については基本目標やKPIが5年程度の期間で検証・修正されると思われるので、この点は共通している。しかし、地方創生政策で最も重要な結果は人口であり、最終的な結果は(目標ではないかもしれないが)人口ビジョンに掲載されている2060年の状況である。人口は特定の政策で決まるものではないし、政策だけで制御できるものでもないだろう。しかも、これから約半世紀という長期間にわたって、最も重要な結果として把握しなければならない。こうした取り組みは政策評価にはない「未開の地」である。政策評価で実践されてきた「検証と修正」を「長期・総合的な」形で行うことは、地方創生政策の重要な課題と言えるだろう。
地方創生政策が成功するのか、それとも失敗に終わるのか-すでに議論百出の状況であるが、個々に見れば効果の高い政策もそうでない政策もあるかもしれない。政策とは別の要素が重要な影響を与える可能性もある。重要なのは「人口」という最も重要な結果に対して、「長期・総合的な検証と修正」を来年から粘り強く続けていくしかない、ということではないだろうか。
御食国、小浜市を訪ねて
先日、久しぶりに福井県小浜市を訪ねることができた。同市がある若狭地方は、古代から日本海を隔てた対岸諸国との交易が開け、日本海側屈指の要港として栄えてきたといわれる。陸揚げされた大陸文化や豊富な海産物、塩など各地の物産は、陸路、若狭と京を繋ぐ数多くのサバ街道を経て、近江、京都、奈良あたりにもたらされた。1500年前には成立していたといわれる若狭国と大陸とのつながり、奈良や京都との古くからの交流の足跡は、市内に点在する数多くの文化遺産からうかがい知ることができる。また、生きたゾウが日本へ初めて上陸したのも、記録上、若狭国小浜が最初といわれ、ちょうど1408年(応永15年)のことと聞いている。
鎌倉時代には執権である北条氏自身が若狭の守護職を務めていたが、鎌倉幕府と北条氏の滅亡後は、北条氏を倒し武家の棟梁となった足利氏の最有力氏族である斯波氏が統治するなど、その時代時代の室町幕府の実力者か、それに連なる人物が若狭の守護職を得ていた。例えば、室町時代初期には一色氏が、その後は安芸国分郡守護の安芸武田氏から分出した若狭武田氏が、若狭武田氏が衰退すると越前朝倉氏の庇護を受けた時代もあったようだ。その朝倉氏も尾張守護代より台頭した織田氏に滅ぼされて、その後は丹羽長秀が支配し、本能寺の変の後、織田信長に代わって豊臣秀吉が政権を握ると、若狭国は山内一豊などの秀吉の子飼いの大名が治めるようになった。
江戸時代になると、京極高次が若狭を領することとなり後に越前敦賀郡を含む若狭地方一帯は小浜藩領となった。又、江戸時代には北前船が若狭地方を本拠地とした為に、敦賀と並んで小浜は海運の一大拠点として大いに盛えた。また、小浜と京都を結ぶ数々の街道がサバ街道と呼ばれるようになったのは江戸時代に入ってからと聞いている。この頃、特に鯖の水揚げが多かったためであろう。そして、1634年(寛永12年)、それまで武蔵国川越城主であった酒井忠勝が入封し明治維新まで続く。特に、酒井家の時代には、色漆を用いて貝殻や卵殻などを塗り込め、研ぎ出しの技法で模様を出す若狭塗を藩の殖産興業として奨励した。また、若狭地域の多くの寺の修復も行った。現在まで、若狭塗は伝統工芸品として続き、地域には古い寺社仏閣が残されているが、これらは酒井家の力によるところが大きい。そのほか、江戸時代を通じて歴代藩主は学問を盛んに奨励した。人材育成に重きを置いた小浜藩の方針は、江戸時代後期になるとみごと開花し、解体新書(ターヘル・アナトミア)を出した杉田玄白、中川淳庵をはじめとする優れた才能を持つ家臣を多く輩出した。1774年(安永3年)に酒井忠貫が若狭に設立した藩校「順造館(じゅんぞうかん)」は福井県内で最も早く開校され、ここで学んだ人々の中には、国学者の伴信友、幕末の志士の指導者、梅田雲浜などもいた。
明治維新により小浜県が設置されると当地はこれに属することとなる。そして、敦賀県、滋賀県を経て1881年(明治14年)に福井県に編入された。1889年(明治22年)の町村制度実施に伴い小浜町が生まれ、その後、1951年(昭和26年)3月、1町7村の合併により若狭の中心都市として小浜市が誕生、次いで同30年、さらに2村を編入し現在の小浜市(人口30千人)となっている。
ところで、同市が誇る産業と言えば、400年以上の歴史を持つ塗箸の生産を挙げなければならない。現在、日本の塗箸のなんと80%以上がこの地から生産されていると聞く。そしてもう一つ、同市が代表する特産物といえば、「へしこ」、「ぐじ(甘鯛)」、「若狭カレイ」など。これらは、全国に知られる高級ブランドとなっている。そして、これらに共通するキーワード「食」を生かしたまちづくりも興味深い。地域の歴史、文化、風土は「食」にあるとし、健康、教育、福祉、環境、産業、観光など、あらゆる分野のまちづくりが「食」を起点に取り組まれているのである。「食のまちづくり」の総合的な課題に取り組むために、2001 年9月には全国で初めて「食のまちづくり条例」も制定された。そして、今、小浜市では食と産業・観光とを結びつけることで地域経済の活性化をめざす、様々な取り組みが行われている。2011年に策定された小浜市の「第5次小浜市総合計画」には、”「夢、無限大」感動おばま”のテーマが飛び込んでくる。そこには、自然と文化があふれる小浜だからこそ可能な地域力を生かして次代を築こうとする小浜人の気概を読み取ることができる。同市の今後の発展に期待したいところである。平成27年国勢調査を終えて
およそ1か月前に平成27年国勢調査が実施された。今回の調査はインターネットでの回答が大規模に宣伝・実施されたこともあり、これまで以上に注目を集めた感がある。筆者もインターネットで回答したが、調査票に記入するスタイルより時間もかからず、とても簡単であった。皆様はどの方式で回答されただろうか。
国勢調査は、我が国に居住する全ての人を対象として実施する国の最も基本的な統計調査であり、大正9年(1920年)から終戦直後を除いて5年ごとに実施されてきた。平成27年国勢調査は20回目に当たる。そんな国勢調査が抱える最近の課題が、調査結果における不詳の大幅な増加である。従来の国勢調査は調査員が各世帯に調査票を配布し、取集するという方法を取っていた。その際、調査員が調査票の記入状況を確認し、未回答や誤回答をチェックしていたために、最終的な調査結果において不詳の発生が抑えられていた。しかしながら、昨今のプライバシー保護の考えのもと、調査員による記入内容の確認に抵抗感を示す人が多くなり(調査員が近隣住民であることも理由の一つ)、またオートロックのマンション等で調査員が各戸に直接訪問することができなくなるケースが増えるなどの影響等もあって、結果的に不詳が多く発生するという事態となっていた。さらに若年層、単独世帯で調査票の回収率が低いなど、不詳が発生する属性に偏りがあることも問題であった。全数調査である国勢調査の精度が大きく揺らいでいたのである。
こうした変化の中で前回の平成22年国勢調査では、東京都全域をモデル地域としてインターネット回答方式が導入され、ICTの活用による調査の効率化が図られた。インターネット回答方式のメリットは未回答、誤回答があると次のページに進めないため、不詳が発生しづらいということがある。さらに東京都におけるインターネット回答の割合は8.3%で、比較的年齢階級が低い層からの回答が多かった。不詳が発生しづらいこと、若年層を中心とした回収対策として期待されることから、インターネット回答を推進するという方向性になり、今回の平成27年国勢調査のインターネット調査の全国展開に至ったのである。
平成27年国勢調査は、インターネット回答期間(9月10日から20日)が調査票での回答期間(9月26日から10月7日)に先行する「先行方式」がとられた(平成22年調査の東京都では、インターネット回答期間と調査票による回答期間が同期間である並行方式)。調査実施前の総務省によると、インターネット回答数は1,000万世帯を超え、世界的にみても最大規模のオンライン調査になることが想定されていた。後日発表された調査結果ではインターネット回答数は1,918万世帯で、調査前の予想を大幅に上回っており、前回の国勢調査の世帯数を基に計算すると、インターネット回答率は36.9%にのぼっている。このうち、スマートフォンからの回答は12.8%であり、インターネット回答のおよそ3世帯に1世帯に当たる。非常に高いインターネット回答率であるが、都道府県別に見た場合には沖縄県の22.7%から滋賀県の48.4%まで開きがあり、地域差が大きいのも興味深い結果である(スマートフォン回答率は東京都7.8%から滋賀県16.7%)。いずれにせよ、想定以上のインターネット回答率であり、最終的な調査結果を見ての判断にはなるが、次回以降の国勢調査でもインターネット回答が大きく推進されていくことは間違いないだろう。
しかし、一方でオンライン調査における課題も散見された。懸念されていた成りすましサイトが実際に作成されてしまった問題やインターネット回答のIDが記載された用紙が封をされずに不用意にポスティングされていたという管理上の問題、回答時に使用できない漢字がある問題など、小さなものからオンライン調査の信頼性が揺らぐような大きなものまで様々な課題があった。それらが想定の範囲内であるか、新たな対策を練る必要があるのかといったことが、次回国勢調査までに検討されていくことだろう。
繰り返しになるが、国勢調査がオンライン調査に舵を取った大きな理由の一つは、インターネット回答が増えることで調査結果の不詳が減り、より信頼できるデータを得られると考えたことにある。最近の国勢調査では配偶関係、世帯の家族類型、就業状態等の不詳が特に多くなっており、少子化の背景にある未婚率の上昇や高齢化社会の内実を把握するのに必要な高齢者の居住状態、就業状態などが正確な情報として得られなくなってしまっていた。これは現状理解の困難もさることながら、将来に目を向けると、これから多額の予算を投入して実施される予定の人口減少や地方創生に係る一連の施策によって発生してくるであろう、若年未婚率の上昇、女性の労働力率の上昇、アクティブシニアの社会参加状況の変化、若年層や高齢層の人口分布変動(東京一極集中の是正)などの様々な変化を正確に把握できないために施策の効果を測ることが困難になることにもつながりかねない。国勢調査に限らず、様々な公的調査への回答率が下がっており、調査結果に不詳が増加している背景には、プライバシー保護の潮流に加えて、年金情報流出等に見られる政府に対する信頼の低下があるように思われる。政府はこうした国民の疑念を解消するべく行動するとともに、そうした状況において最良の結果が得られるように調査の実施方法を考えていくことが求められる。恐らくオンライン調査がその一端を担っていくことだろう。平成27年国勢調査の結果がどのように集計されるのか、非常に興味深いところである。もちろん不詳が減り、調査結果の信頼性が向上すること、そして次回以降の国勢調査にもつながっていくことを一研究者として願ってやまない。「グローバル人材」育成策としての海外出張
ここ数年のうちに、「グローバル人材」ということばが広く言われるようになった。定義や要件にはさまざまな意見があるが、日本企業が海外ビジネスを開始、成功、拡大するために貢献する人材、と考えて差し支えないだろう。海外展開に取り組む企業には、こうした人材へのニーズがある。日本貿易振興機構(ジェトロ)が2015年3月に発表した日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査では、海外ビジネス拡大のための人材戦略をたずねたところ、「現在の日本人社員のグローバル人材育成」と回答した企業が45.1%と最多であった。
しかし、回答比率は、大企業では68.7%、中小企業では38.4%と、企業規模によって、人材育成を重視する企業の数に差がみられた。人材育成への取り組み方についても、最多回答は「国内で英語研修の充実を図っている」が21.4%だったが、大企業では47.2%、中小企業では14.1%と、取り組みに濃淡がみられた。以下、「OJTにて行っている」は21.3%で、大企業36.3%、中小企業17.1%。「若手社員を一定期間、研修生として海外子会社等に出している」が10.6%で、大企業32.7%、中小企業4.3%。そして、「特別な取り組みは実施していない」との回答は41.9%であったが、大企業では17.1%であったのに対し、中小企業では49.0%と半数近くにのぼった。
こうした結果からは、大企業に比べ、中小企業ではグローバル人材育成の取り組みはなかなか進んでいないことがうかがえる。では、中小企業にとって、どのような育成方法なら取り組みやすいだろうか。
過日参加したフォーラムで、早稲田大学教授の白木氏はグローバル人材の育成に関して「ある企業では、若手社員に会社の代表として海外出張に一人で行かせている。自分で航空便やホテルの手配を含め全ての関連業務をやることで、非常にいい教育になっているとのことだ」という事例を紹介した。この方法は、グローバル人材に求められる能力を伸ばすことが期待できるし、業務の中で行うものであるため中小企業にも取り組みやすいものと思える。
「グローバル人材に求められる能力」についてはさまざまな意見があるが、例えば、経済産業省が2010年4月に発表した「産学人材育成パートナーシップ グローバル人材育成委員会」の報告書では、「社会人基礎力」、「外国語でのコミュニケーション能力」、「異文化理解・活用力」が挙げられた。「一人で会社の
代表として海外出張」は、このすべての力を試される場だといえる。会社の代表としていくからには、業務内容を十分理解し、訪問先での業務を問題なく進めなくてはならない。面談相手が外国人なら外国語が必要であり、面談時に通訳が同席したとしても、空港やレストラン、ホテル、タクシーなど外国語が必要になる場は多い。若手社員は、「社会人としての基礎力」を発揮して業務に取り組み、時に「外国語でのコミュニケーション能力」を使う。そして、外国に身を置くことで「異文化理解・活用力」を鍛えることになる。
海外出張には市場視察、見本市出展、取引先・提携先との商談、海外拠点訪問など、いろいろな機会がある。そのため、これを人材育成の手段にすることは、中小企業でも大企業でも難しいことではない。もちろん、既に「海外出張は社員がグローバルな経験を積む好機」と捉えている企業は多いだろう。しかし、若手社員を一人で、しかも「会社の代表」として出張させることは少ないのではなかろうか。出張する社員にはプレッシャーもあろうが、それは適切な負荷となり、成長を促すことができる。こうした海外出張は経験値を高めるのみならず、必要な能力を発揮せざるを得ない機会となり、グローバル人材の育成方法として活用することができるだろう。
なお、一人での海外出張が難しい場合は、上司や先輩とともに、となってもかまわない。ただその場合、若手社員は、単なる「カバン持ち」などとしてではなく、習得すべき事項を設定したうえで、明確な目的・目標を持ち、一定の役割を担うことが望ましい。そうしてこそ、海外出張がグローバル人材としての力を伸ばす方法として効果を発揮するものと考える。ふくい地域経済研究第21号
プレミアム商品券に関する考察
1.前回の「ふるさと商品券」の効果
2010年度に実施された「ふるさと商品券」は、総額1.7億円のプレミアムにより7.2億円の消費が新たに創造されたと推計された。この新たな消費喚起額は、商店の売上増に直接的に貢献するとともに、これら商品の原材料生産等を誘発することにより、間接的に県内外の多様な業種へと効果が波及している。
新たな消費喚起額がプレミアム額を大きく上回った要因としては、期間限定のお得感が、欲しかった商品を購入するきっかけとして、県民の消費マインドを刺激した結果と推測される。すなわち、ペントアップ・デマンド(景気低迷下で抑制されてきた需要)と近い将来の需要が、このふるさと商品券により顕在化した可能性がある。
また、県外やネット販売への消費流出を、地域限定の商品券により食い止める効果と、県下全17地域で実施された消費拡大イベントとの相乗効果も、一定程度あったものと評価される。日常に比べて商店街での利用割合が高くなるなど、消費者が地元商店街に目を向ける契機にもなったのではなかろうか。
2.今回の「プレミアム商品券」に関するポイント
プレミアム商品券の利用により、その期間中は一時的に消費が拡大するとともに、地域小規模店へと一部の消費がシフトする。これを単なる需要の先食いや一時的なものとしないためにも、この効果を好循環させるための工夫が各方面に期待される。
商店側には魅力的な商品づくり・店づくりに加え、ふるさと商品券の取り組み効果を踏まえた積極的な仕掛けづくりも重要になる。地域小規模店は販売促進や商品・サービスの質を向上させるきっかけとするとともに、普段、大規模店を利用している消費者に対し、プレミアム商品券の利用を契機に、大規模店とは違う価値を提供しないといけない。例えば、こだわりの品揃えであるとか、痒いところに手が届くようなサービスであるとか、マニュアルにはない心からのおもてなしやコミュニケーションとかがポイントとなろう。
個人消費はGDPの約6割を占めている。消費税率引上げで落ち込んだ個人消費を、行政による補助で浮上させようとする施策自体は意義のあることである。期間限定や地域限定による効果は確実にあり、福井県が行っている「福井県プレミアム藩札」もまた地域経済への波及効果が一定程度生じるであろう。しかし、行政はそこから一歩進めて、その動きを持続的な確かなものにするための後押しをする必要がある。各地で消費拡大イベント等を仕掛けて、地域のお店とのふれあいや地域の産品を手に取る機会を創出して、「買物の楽しさ」や「地域の商品やサービスのぬくもり」等を再発見することに結びつけることで、息の長い消費拡大につながるのではないか。ギリシャ危機があぶり出すEUの不協和音
この原稿執筆時では、経済危機にあえぐギリシャへの金融支援がようやくまとまり、ユーロ圏からの支援としては第3次となる、820億ユーロ(約11兆円)が融資されることが決定したとされる。噂されていたGrexit(ギリシャのユーロ離脱)を避けるためのぎりぎりの選択であったと思われる。しかしこれで5年ごしのギリシャ問題に一件落着となるかは、甚だ疑問があるだろう。ギリシャの公的債務は3,100億ユーロ(約42兆円)であり、今回の支援が実施されるまでのつなぎ資金の問題なども残っており予断は許さない。
意外かも知れないが、ギリシャは単年度の財政均衡をほぼ達成している。これまでの財政緊縮政策で財政赤字は大幅に減少したが、厳しい緊縮策のため2009年から2014年にかけてGDPが25%減少した。その結果、政府債務残高のGDP比率は大幅に悪化するという皮肉な結果になっている。そうなると元本削減(ヘアカット)という手段しか残されていないように思われるが、これは原則的にはEU条約など法律の縛りがあり難しいとされてきた。
EU主要国の中でギリシャ支援に対して最も厳しい立場をとっているのはドイツで、ギリシャはさらなる財政緊縮政策をとるべきであると主張してきた。ドイツ=勤勉、ギリシャ=怠惰、というステレオタイプのイメージがあるのも事実であろう。しかしここにきて「ドイツ責任論」が、日本を含む世界各国で浮上してきている。今やドイツは欧州の中でも圧倒的な経済力を誇り、独り勝ちと言っても良い状況にある。イギリスメディアなどによってドイツは第4帝国を築いた、と言われる所以でもある。
本来、経済学的には国際収支の自動調整機能によって為替レートは変化し、一国の輸出競争力は必ずしも強いまま、弱いままにはならない。しかし2002年ユーロ圏が実施した共通通貨制度によって、事実上各国の金融政策は無効化し欧州中央銀行(ECB)にその権限を移譲することになった。アジアにおける唯一の制度的な共同体であるASEANは共通通貨制度の採用を検討しておらず、ユーロとEUは壮大な実験であるとも考えられてきた。当初安定していたユーロであったが、リーマンショックと前後して2008年頃から財政基盤の弱い南ヨーロッパ国など、いわゆるPIIGS(ポルトガル、イタリア、ギリシャ、スペイン、アイルランド)が問題視されるようになり、2010年のソブリン危機につながる。その過程でユーロの為替レートは大きく下がり、「弱いユーロ」の利益を最も享受したのが工業国ドイツということである。
ギリシャでは2015年1月の総選挙で急進左派連合が勝利し、債務問題でEUとの対決姿勢を強めた。チプラス首相がドイツに対して戦時賠償を持ち出した際には、日本人の感覚からすれば馬鹿げたことに思えたが、実際ドイツは1950年代に戦時債務の60%を免除されたという歴史をもつ。その後、欧州共同体、欧州連合と進むことによって、地域統合はアジアとは比較にならないレベルに達していることから、本来ギリシャ危機はEUの「一地方」問題として解決されるべきと考える向きもあるだろう。しかし実際には国家的アイデンティティの強さから、妥協を拒む姿勢が各国それぞれの形で噴出している。アジアにおいても数年間まで「東アジア共同体」が議論される機運があったが、先行している欧州においてもこうした問題に方向感がなく、七転八倒している状況を良く見ておく必要があるだろう。
人口からみた選挙制度と年齢
諸制度には適応される対象年齢が定められているものが多い。
6月17日に18歳以上に選挙権を与える改正公職選挙法が成立した。安全保障関連法案の議論に隠れてあっさりと可決された感がある。経過はさておき、これによって来夏の参院選では、日本の歴史上初めて18、19歳の未成年者が国政選挙で投票することになる。
来年の18、19歳人口はあわせて約240万人。日本のような先進国では乳幼児ならびに若者の死亡率は低い。さらに、国際人口移動が相対的に少ないわが国では、出生時の人口と数年後、十数年後、少なくとも成人期までの当該年齢人口が概ね一致する。よって、今から17、18年前の出生数(1997年119万人、98年120万人)をみれば、将来人口推計など難しそうなことをしなくても、制度変更によって影響を受ける人口の概数くらいは誰にでも見当がつく。
ただし、地域別には状況が異なる。死亡率には全国的にさほど大きな地域差がないものの、選挙区間を跨ぐ人口移動は激しい。とりわけ大学進学時に移動する若者が多いことは皆さんもお気づきであろう。今日の日本の若者は男女とも半数が大学に行く。地元の高校生が卒業後に域内の大学に行くのか、域外の大学に行くのかによって、地域の人口は大きく変わる。当然のことながら、新たに選挙権を得る18、19歳人口が多い地域と少ない地域が出てくる。大学数の最も多い首都圏、福井県からも近い京都や大阪の大学には全国から多くの若者が集まる。単純に考えれば、今回の選挙制度の変更によって、”一票の格差”はこれまで以上に広がることになる。今回の制度変更は”一票の格差”是正を目的としたものではないことが分かる。では何が目的なのであろう?
人口の年齢構成からすると高齢化が進むにつれて選挙権を持つ人口(現行20歳以上人口)に占める高年齢者の割合が高くなり、若者の声が政治に反映され難くなっていることへの対応とみる向きもあるが、今後18、19歳の新たな参入によって投票状況を含めた選挙の在り方が変わるのか否か、今後の実績をしっかりと検証し見極める必要がある。
ちなみに、選挙権は選挙人名簿に登録されている地域で与えられる。所管官庁の総務省のHPでは、”選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満20歳以上(※これが今回18歳以上に変更される)の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です”と書かれている。要するに、住民票を異動させなければ、域外の大学所在地で生活していたとしてもそこで投票する資格は無い。逆に言えば、投票したい地域に住民票を残しておけばそこに住んでいる実態がなくても投票ができる。なお細かいことを言えば、住民票の異動後3か月以上経っていなければ選挙人名簿に載らないので、来夏の参院選がいつ行われるか、いつ住民票を移すかによって、当地の選挙権が得られるか否かが決まる。
選挙法が改正された日の夕刻NHKの福井県版ニュースを観ていると、福井県知事の西川氏が”ふるさと投票”と言っておられた。福井県外で進学したり就職したりしても生まれ故郷の政治や行政に関心を持ち続ける若者が増えることはとても大切だと思う。”ふるさと納税”同様、地域社会を支えるツールの一つに繋がれば望ましいと考える。余談だが、上述のNHKのニュースでは的外れなコメントがされていた。確か、福井県においては住民票登録人口よりも戸籍簿に登録されている人口が多いので、”ふるさと投票”の知事のアイデアは今後18、19歳の若者の地元関心を高める妙案である、とか。個人の戸籍がどこに置かれているのかと選挙制度とは全く関係がないので、何を言おうとしているのか私にはよく分からなかった。
ちなみに、議員定数は5年に一回行われる国勢調査の結果をもとに更新される。今年の数か月後の10月1日が調査日だ。ただ、国勢調査は現住地で国民の状況を把握するもので、住民登録とは直結していない。選挙で選ぶものと選ばれるものの人数が異質の人口統計をもとに決められている。今回の公職選挙法の変更を機に若者の投票への関心についての議論が盛んに行われているようであるが、わが国の選挙制度には私たち”大人”がまずしっかりと考えなければならない課題が少なくないように思う。
現地化について考えること
およそ過去30年、日本からアジアに進出する日本企業(製造業)は海外子会社で管理職を担う幹部人材の「現地化」が遅れていると批判されてきた。しかし、現時点でもなお現地人をマネジメント層に登用するという動きはあまり進展がみられない。この「現地化」という言葉は、その含意として「日本人中心の経営の弊害」、「現地人への事業運営の移管」、「日本人ゼロ」、「現地人の経営参加」といった事柄がイメージされる。しかし、現地化を推進することのリスクも決して小さくない。しかし、国内外の研究者の多くはそのリスクを過小評価し、「日本人中心の経営の弊害」ばかりを指摘してきた。
ここで言う「日本人中心の経営の弊害」とは、海外子会社の主要な意思決定のポストに現地駐在の日本人スタッフがつくために現地人の「モチベーション」が停滞するとか、有能な現地人の「確保・定着」が困難になるとか、あるいは、給与水準の高い日本人スタッフに頼った事業運営は「日本本社側のコスト」の増大につながるとか、「現地適応する」にも敏感に現地の市場ニーズをキャッチできないとか、様々な問題を意味している。
いずれも「日本人中心の経営」特有の問題であるが、逆に、「過度の現地化」(=日本人スタッフを減らしすぎること)にも次のようなリスクが潜んでいるのも事実である。海外子会社がグローバルな視点を持つことが難しくなること、日本人に海外経験を積ませることが難しくなること、日本本社が海外子会社をコントロールすることが難しくなること等がそれである。
つまり、日本の進出企業がマネジメント層の現地化を考える際、「日本人中心の経営の弊害」と「過度の現地化」に潜伏するリスクの両面を勘案する必要があるということである。
この課題に対して日本の進出企業はどのようにして対処しているのか。一例であるが、インドに現地子会社を持つ日系自動車部品メーカーでは、当該子会社の経営トップが「現地人」であり、「労務管理」、「営業」を担当している。それ以外の「技術・品質面と資金面の管理」は「日本人スタッフ」が責任をもつ。つまり、経営トップは「現地人」であるが、同社の場合、管理項目の主要な柱である、品質、財務面については「日本人スタッフ」に責任を持たせることで、海外子会社が本社の意向を無視して独走することに対して一定の歯止めの管理を行っている。したがって、経営トップが「現地人」であると言っても字義通り「現地人」が海外子会社の管理を行う完全な権限を持っているわけではなく、一定の管理権限は「日本人スタッフ」が握っているのである。
このように、「現地化」という言葉は聞こえがよく、「日本人中心の経営の弊害」を意識させ、現地人に経営を任せればうまく行くという考え方の普及に寄与した。しかし、実態は日本人スタッフが担っている高いポジションを現地人に全面的に任せる例はあまりみられない。現下の日本の進出企業の本音をあえて言えば、「経営が上手く行けば、現地人であろうが日本人であろうが、誰が経営しようが、たいした問題ではない」。現地化というよりも、経営管理をしっかりして着実に利益を上げることのほうに注力するという状態が続いているのである。地方自治から見た地方創生の2つの問題
筆者が前回担当したコラムでも地方創生について述べたが、今月実施された統一地方選挙では地方創生のあり方が総じて重要な論点となったほか、投票の結果とともに投票率の低下や無投票当選なども大きく報道された。そこで、本コラムでは地方自治の観点から再び地方創生を取りあげる。
すなわち、地方創生に向けた取り組みが国・地方ともに進められているなかで、地方に対する関心が高まりつつあると考えられるが、選挙を通じて逆の傾向があることも見出された。この点について、地方自治の見地から次のような2つの問題が提起されるのではないか。それは、地方創生と、地方自治の2つの側面である団体自治と住民自治の関係である。団体自治とは、国と地方自治体の関係を示すもので、国の関与が少なく地方自治体が主体性を発揮できる状況を表す。また、住民自治とは地方自治体と住民の関係を示すもので、住民の意思に沿った政策を地方自治体が実施する状況を表している。
まず、団体自治と地方創生の関係を述べる。地方創生では地方の主体性が期待されており、その意味では団体自治に即した政策形成が尊重される形になっている。しかしながら、地方創生が求められる背景は地方圏から大都市圏への人口流出であり、その大きな要因は景気の動向である。日本創生会議の資料によると、景気が良い時期に人口流出が顕著になっている。また、総務省が4月17日に発表した2014年10月1日現在の人口推計でも東京圏への一極集中が進み、アベノミクスの効果と分析されている。したがって、ごく単純に考えれば、地方の人口流出を逆転させるためには景気の動向を転換することが必要になるのだが、それは地方の主体性で実現するものではない。日本の経済成長の構造を根本的に変革することが必要だとすれば、むしろ国の主体性が問われるだろう。団体自治とは地方自治体が主体性を発揮する状況であるが、それは地方に求められる役割についての話である。国がなすべきことは国が責任を果たさなければならないのであり、地方創生に関して地方の主体性が過剰に期待されたことが、かえって関心の低下を招いた、という見方ができるのではないだろうか。
第2の問題は、住民自治と地方創生の関係である。選挙は地域住民の投票によって代表を決めるものであるから、最も強力な住民自治の制度である。したがって、選挙への関心が低下していることは、住民自治の後退として懸念材料となる。とりわけ、各地の選挙管理委員会が投票率の向上に向けて若年層向けの啓発活動を積極的に行ってきたが、十分な成果をあげることはできなかったようである。地方の問題に関心を持たない若年層が増えることは、住んでいる地方への愛着や参加の意思が乏しい状況を表しているだろう。だとすれば、彼らも大都市圏に流出する可能性がある。また、人口減少が地方消滅という衝撃的な警告となったことで地方創生が各地で進められているが、地方創生の成果として人口増加まで求めることは困難であろう。だとすれば、積極的な人口減少対策とともに、規模の縮小を前提とした財政運営の新たなビジョンを提示する必要があったのではないか。地方創生を住民自治の視点から捉えるならば、中心的なものが経済政策であるとしても、その基盤にあるのは地方の個性や住民の存在である。短期的な政策に加えて、地方創生に向けた中長期的な対策を住民とともに考え、実行していく体制づくりが必要ではないだろうか。選挙に対する関心の低下は、このことを示唆しているように思われる。
筆者は地方創生の重要性を否定しているのではない。むしろ、きわめて優先度の高い政策であるからこそ、各地で斬新な地方創生策が数多く表れることを望んでいる。地方創生が求められる背景と経緯、国と地方の役割、行政と住民の役割を踏まえてこそ、実効性と持続性のある地方創生が実現すると考えられる。