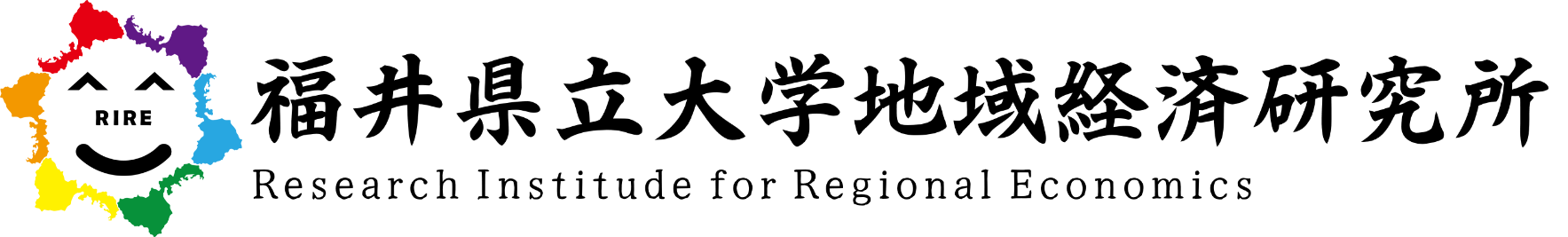2014年
2015年、地方創生への不安と期待
12月14日に行われた衆議院総選挙の結果、自民党連立政権が継続することになった。約2年続いた「アベノミクス」と呼ばれる経済政策も、引き続き推進されていくだろう。同時に、積年のさまざまな懸案事項についても正面から対策を進め、具体的な成果の獲得を図ることが期待される。
2015年に地域の視点で重視されるのは、地方創生であろう。これは「ローカル・アベノミクス」と呼ばれる現政権の新たな取り組みであるとともに、「東京一極集中の是正」という長年の課題への対応でもあり、いずれの視点でも重要と考えられている。
しかし、両者は必ずしも同じ方向性を持つものではない。なぜならば、ローカル・アベノミクスでは大都市圏で先行した経済成長の恩恵を地方に波及させることが重視されているが、これまで東京一極集中が進んできた主な要因は東京を始め大都市圏が成長の核になったことにあるからである。したがって、ローカル・アベノミクスが地域経済の成長をもたらしたとしても、それが東京一極集中の是正に結びつくとは限らないだろう。東京一極集中を是正するためには、東京ではなく地方から日本の経済成長を牽引する構造に改めるくらいの姿勢が必要ではないだろうか。
この点に関連して、地方創生の具体策について考えることにしたい。報道で明らかになった具体策に対して、筆者は不安と期待のいずれも持っている。不安の1つは、交付金構想である。これは、地域の消費を活性化させるものと、人口減少などですぐれたアイデアを出した自治体に配るものの2種類がある。例えば、前者は商品券や旅行券、後者はIターンや企業誘致などが交付対象になるという(12月18日付朝日新聞)。これらは、大都市圏の成長の恩恵を地方に波及させるものであるとともに、地域振興券や頑張る地方応援プログラムなどの前例もある。そのため、東京一極集中の是正まで見すえるならば、交付金構想が十分な成果に結びつくかどうか、不安である。
一方で、期待できる施策もある。それは、本社機能の地方移転に対する優遇措置である。かつて「地方分散政策が東京一極集中を招く」という逆説的な状況が起こっていることが注目されたが、その原因は東京における本社機能の強化にあった。今回の地方創生では、管理部門などの本社機能の移転に伴う社員の転勤などで地方拠点の雇用が増えた場合、法人税額が控除されるなどの優遇措置が検討されているという(12月18日付日本経済新聞)。これは、従来にない新しい取り組みであり、実際に成果を挙げられるかどうかは未知数だが、東京一極集中の是正まで見すえた施策として筆者は期待を持っている。
こうしてみると、地方創生については、短期の視点と長期の視点、大都市圏と地方圏の関係、そして地方の役割と国の役割など、トレードオフの問題を含む複雑な構造を理解したうえで、発想の転換が求められる。不安と期待が入り混じるなかで、2015年は地方創生がどこまで成果をあげられるか。期待が現実になることを願っている。
軍事政権によって「安定」を取り戻したタイ政治
前回5月のコラムに書いたタイ政治のその後について触れてみたい。5月22日にタイ陸軍による8年ぶりのクーデターが発生し、その後は軍事暫定政権となっているのはご存じのことかと思う。結論から言えば、現時点で戒厳令が継続されているとは言え治安を取り戻しており、各交差点でバリケード封鎖が頻発した今年初めの状況からすれば秩序と安定を回復したように見える。但しこれがつかの間の安定になるかならないかは、今後の情勢を待たねばなるまい。
ここまでの2000年以降の状況を整理すると、2001年のタクシン政権成立、2006年のクーデター・タクシン亡命、2011年のタクシン実妹のインラック政権成立、2014年のクーデター・軍事政権成立、となる。タクシン=インラックによる政策の基本となった農村振興と農村部低所得者への手厚い支援は、バラマキと強権、汚職、縁故主義と表裏一体のもので、タイにおける従来の既得権益者、エスタブリッシュメントにとっては大変不愉快なものであったのは間違いなかった。タイを最も不安定にしたのは、低所得者層を中心としたタクシン支持派が総選挙で常勝するようになったことで、従来のタイでは見られなかった政治的立場による国民の二分化という現象が表面化したことである。またタイ国民の心のよりどころで、政治的中和剤でもあったタイ王室への疑問がタイ人の間でささやかれるということもかつてなかったことである。
民主主義の原則に則り、選挙結果を尊重することが何よりも重要であるとの意見はもっともである。しかし多くの開発途上国で経験したように、民主化を推し進めることで多くの犠牲を払うこともある。ましてタイは本来、共産党一党独裁やマルコス、スハルトのような極端な政治体制ではない。5月のクーデターは、国を二分しかねない極めて緊迫した状況の中で発生した。クーデターと軍事政権を擁護するものではないが、あの政治的混乱の中では他に取り得た解決策は限られていただろう。むしろ私は今の軍事政権下における政治はタイにとってチャンスであると考える。タイにおいては驚くことに相続税(あるいは遺産税)は存在しない。この制度の導入について多くの高所得者層が反対するからである。これはタクシン政権下でも同様であった。プラユット暫定首相と軍事政権は経済改革の一環として、相続税の導入を閣議決定し法案化しようとしている。
軍事政権に「世直し」を期待するというのは何とも皮肉なものである。しかしこうした強権の下でしか実現しない政策があるのはタイに限らずあるものだ。とは言え軍事政権が長引けば国際世論の批判を受け、最悪タイ経済は立ちゆかなくなる。タクシンの負の遺産の一つ(と私は考える)は、タイにおける改革の時間を縮めたことかも知れない。国内の深い対立の構図を解消する難題を短時間で目処をつけるのは、ごく細い道を走るような綱渡りに他ならない。こと政治に関してタイ人は実に柔軟な知恵をもって対応してきたという歴史がある。しかしASEANの主要国でもある現在は衆人環視の中、国内外を納得させるだけの結果を出さねばならず、タイは極めて大きな試練に直面していると言えるだろう。
マクドナルドの食の安全対策
昨年以降、中国や台湾で食の安全をめぐる問題が相次いで発覚している。今回は中国で7月に発覚した「期限切れ肉」問題を素材に当事者がどのような対策をとろうしているのかについて、要点を報告しておきたい。
日本マクドナルドによる食の安全対策
7月20日日本マクドナルドホールディングス(以下日本マクドナルド)が取引していた中国の仕入先企業(食肉加工会社)が使用期限切れの鶏肉を使っていたことが判明した。この問題の影響により、同社は既存店売上高が前年同月比で、7月は17.4%減、8月は25.1%減、9月は16.6%減と大幅に落ち込んだ。中でも8月の減少幅は2001年7月の上場以来最大の落ち込みであったという。
この「期限切れ肉」問題をめぐる日本マクドナルドの対応は様々に新聞などで報じられているが、その代表的な取り組みは次の二つである。仕入先企業に対する(ア)抜き打ち監査と(イ)監査レポートの提出の2点である。(ア)は「肉や野菜などの仕入先に年2回抜き打ち監査を始める」というものである。この「抜き打ち監査の対象は、牛肉やレタスなど主要食材を扱っている約30社」であり、「日本マクドナルドと第三者機関がそれぞれ年1回以上実施する」という。従来から監査は存在したが、「予定日を知らせていた」。これに対して、「予定日を知らせない」抜き打ち監査の導入により、「予定日を知らせていた」従来の仕組みに比べ、より「品質管理を強化」しようとしている。他方、(イ)の監査レポートの提出は「仕入先に対して、原料を調達している企業などに定期的に監査することを義務付け」るというものである。当該仕入先に「その結果をまとめた監査リポート提出も求める」ことより、当該仕入先のみならず、その「原料調達先が、マクドナルドの定める管理基準をクリアすることも求め」ている(『日本経済新聞』2014年10月4日)。
このように、直接の仕入先だけではなくて、原材料の調達先にまでさかのぼり監査を徹底して品質管理を強化しているのである。仕入先企業独自の食の安全対策
以上は発注先である日本マクドナルドによる安全性や品質の管理体制の強化の取り組みであるが、安全性や品質の問題は、結局は、実際に物づくりを行っている(仕入先企業の)工場の現場のモラルに委ねられる面が大きい。
この点にかかわって、注目したいのが、使用期限切れの鶏肉を使っていた中国の加工工場で働いていた元従業員の次のような話である。同工場で働く従業員の仕事の内容は「室内温度4度という劣悪な環境下で」「保温服に防護具区を重ね、マスクに手袋の重装備をし、」「管理マニュアルが求める細かいルールに従」わなくてはならないというものであった。しかし、そうした労働負荷が課されるにもかかわらず「まじめな働きぶりを発揮したとしても、手にする月給はたった2000元(約3万2000円)でしかなかった。」従業員個々人の働きぶりに報いる動機付けや賃金インセンティヴを欠いているのである。だから同工場から「多くの従業員が離れた。」例えば、かつては安全性や品質に関して「厳しく指導する先輩」がいたが、徐々にこの人々「も姿を消し」た。また「新規採用の従業員も定着せずに辞めて行った。」(『DIAMOND on line』2014 年8月1日)
同工場は徹底した人件費コスト抑制を追求してきたために、従業員から最低限の協力しか確保し得ず生産現場の安全性・品質への対応が疎かになったというわけである。専ら人件費のコスト最小化を追い求めてきた経営者たち(同工場の経営陣、その上の米国にあるOSIグループ本社の経営陣を含めて)は、この問題に対しいかなる方策を用意しているのであろうか。
日本マクドナルドは確かに「期限切れ肉」の問題が発覚した直後に当該仕入先企業との取引を全面停止した。だが、この食品の安全衛生問題は当該企業に限った話ではない。中国国内の他企業、ならびに中国以外の国々(日本を含む)でも、程度の差はあれ、有り得る問題である。
日本マクドナルドが再び同様の問題をおこさないようにするためには、上に紹介した発注先(この場合、日本マクドナルド)による管理体制の強化だけではなく、仕入先それ自体の管理体制の強化の推進も不可欠である。企業間取引関係から(企業内)雇用関係を含めた全体の体質改善問題として受けとめなくてはならないからである。ふくい地域経済研究第19号
求められる地域中小企業の経営革新
近年の構造変化を眺めてみると、エネルギー・環境問題、市場の多様化・高度化、労働力人口の減少など産業基盤を揺るがす様々な変化が進んでおり、その中で地域の中小企業も時流をうまく取り込んだ新たな産業分野への転換が求められている。 例えば、自動車の燃料がガソリンから電気へと転換期を迎え、従来の自動車関連部品メーカーもこれに対応することを余儀なくされている。こうした動きは、新たな技術や商品を持つ企業が、自動車産業へ参入するための一つの機会につながるであろう。また、このような動きは自動車産業だけではない。化石エネルギーから再生可能エネルギーへ、生産の集中から国際分散化へ、環境技術や循環型社会への注目など、今世界は大きな転換点に立たされているのである。つまり、中小企業にとっては、従来の産業システムや生産体系の変化、流通の高度化等の多様な変化の中で新たな経営革新が求められているわけであり、こうしたシステム転換が地域企業、とりわけ製造業にとって大きなチャンスを与えてくれる絶好の機会となるかも知れない。具体的に地域における中小企業の可能性を探るとすれば、福井県はエネルギー関連施設の一大拠点であり、これを活かして環境技術の開発を集中的に進める、あるいは戦略的な支援を行うといった方針を地域全体で取り組むことはできないか。また、地域の農業分野でも変革が必要である。例えば、農のビジネス化、目指すべきは、ビジネスとしての農業、産業としての農業の確立である。その際、製品評価の指標でQCDSという言葉に注目したい。この言葉は、品質(Quality)、価格(Cost)、納期や入手性(Delivery)、対応やサポート(Service)の頭文字をとったもので、製品の調達・購入や商品開発の際の指標として活用されているが、農業分野でもこのQCDSを考え利用していく必要があるように思える。建設業も同様である。日本の建設業の技術や品質は非常に高い。今後、さらに国内需要が減少する中で生き残っていくには、建設需要が高まっている新興国など海外市場を狙うことも必要となろう。その際、品質だけではなくサービスや機動力(デリバリー)を売り物にすることも考えなければならない。その他、内需型産業の代表で地域を支える卸・小売・サービス業等も、大変革が求められている。今、協議が進行中のTPPなどの参加が具体化すれば、地域経済に依存度が高いこれら産業・企業は、これまで以上にグローバル化の影響を受けることが予想されるからである。つまり、「内なるグローバル化」に対し、こうした産業・企業では、先進国と振興国間での技術・ノウハウの相互移動、すなわちリバース・イノベーションの動きを逆手にとり、うまく活用しながら国内需要の掘り起こしに役立てる手法を検討すべきであろう。具体的には、自社の流通そのものを見直し、品質やコスト面で競争力の高い海外品にも目を向けること。そのためには、めまぐるしく変化する国際情勢に対しその情報収集力を高める意味からも、海外企業、海外市場との関係性強化を図る手立てを早急に検討することが重要となろう。
舞若道の効果とそれを生かすための課題
嶺南にとって、長年の悲願であった舞若道が、7月20日に全線開通した。地元の期待も大きく、観光はもちろんのこと、地域経済や人々の暮らしに大きな効果がもたらされる可能性がある。
まず、直接的な効果として、今回の小浜ICから敦賀JCTまでの開通によって、小浜から敦賀が約1時間かかっていたものが30分に、金津ICから大飯高浜ICまでが1時間40分ほどで結ばれる。嶺南の地域内移動が1時間以内になり、県内の主要都市間の移動が2時間みておけば余裕があるという県土構造になった。2時間を切るということは、ノンストップ、もしくはワンストップで行ける距離になるということであり、高速道路で目的地近くまで行けるということは、運転ストレスの低減や定時性の確保にもつながる。これまでは、嶺南を横に貫く道路は国道27号と梅街道だけであり、近距離の移動と広域的な移動を同じ道路でさばいていた。これが、舞若道の開通によって明確に分担され、一般道における交通の円滑化も期待される。次に間接的な効果であるが、舞若道の全線開通によって、福井県を含めた関西と中京地域を結ぶ大きなループ状になった高速道路が浮き上がってくる。環状化によって人や物の流れが大きく変わり、それに伴ってこの嶺南に少なくない影響が生じる。例えば、この環状の高速道路は、観光面において周遊ルートとしてかなり有望になるが、物流面でも大きな効果を生む。環状になるということは、物流ルートが2ルートでき、災害や事故等の際にも迂回が可能となるという利点と、複数箇所を回って効率的に集配ができるという利点がある。これらを生かした物流拠点あるいは生産拠点の嶺南への立地も期待したい。また、東日本から西日本への広域的な物流を考えた場合、日本海側における高速ネットワークの充実・強化にも資するなど、大きな意義がある。
以上のように、舞若道で新たなつながりが生まれ、あるいは、これまでのつながりが太くなることにより、期待される効果は観光分野から物流分野、そして生活分野にまで及ぶ。しかしながらこの期待を確かなものにするためには、受け身で待つだけではなく、この道路整備を生かして地域自らが環境変化に対応していかねばならない。今は、高度経済成長時代ではなく低成長時代にあり、今後は人口減少と高齢化がますます進んでいく。新幹線や高速道路ができれば、それだけでバラ色の未来が描けた時代ではない。また、成功事例の模倣をすれば、同じような成果が導かれるという時代でもない。この高速道路を生かした自立的で個性的なまちづくりを進めていくとともに、誰をつなぐか」、「なぜつなぐのか」、「どこをつなぐのか」、「なにをつなぐのか」、「いつつなぐのか」、「どのようにつなぐのか」ということを、行政が、企業が、地域が、住民が、それぞれ主体的かつ連携を取りながら、戦略的に考えていく必要がある。なぜ学の旅
2012年春に福井県立大学に赴任し教職に就いた。あれから2年と4カ月が経過し、いよいよ任期満了で派遣元のジェトロに帰任することとなった。福井県立大学ではアジア経済を中心に授業を担当したが、これから社会に出ていく若者たちと接する度に思うことは、今の若い人たちが異文化、異質性、多様性に対して不慣れだということである。いや、不慣れというよりも無関心に近い状態でこれまで年を重ねてきた印象すらある。私自身が大学生の頃どうであったかを思い起こせば、自分だって同じようなものだったかもしれない。高校を出たばかりの若者の世界観というのは生活圏内の比重が大きく、他県や外国、異文化はメディアを通じて知ってはいたものの、自分とは縁のないものと考えていた。学生時代の私は大学の授業を通じ、じわじわと外国への憧れが湧き起こったが、学業とアルバイトと遊びで忙しく、旅に出るという行動を起こすまでには時間を要した。大学3年生にもなると、インドや中国を極貧旅行してきた友人が私の周囲にも何人か現れるようになった。学生食堂でこれら友人の武勇伝を聞くうちに「自分も行ってみよう」と功名心のようなものが芽生え、ようやく外国に向けて重い腰を上げたのであった。
現在、インターネットを使ってキーワード検索をすれば、動画、画像、旅行記、歴史背景などを瞬時に観ることができる。行ってみなければわからないという気持ちが萎えてしまうほど内容は充実しており、高い旅費をかけてまで現地に行くまでもなく、他人の報告を見るだけで行った気になるし、分かったような気になってしまうのである。だから、今時の学生は20年以上前の学生と比べ、さらに腰が重くなっている可能性もあるだろう。
旅をするということは自分の足で歩き、肌で空気を感じ、耳で雑音を拾い、現地の人と肩を並べて同じようなものを喰い、そこの人たちと接触してくることである。まさに五感を通じて異質性を感じ取る作業が旅であろう。名所旧跡を訪ねるのもいいが、現地のモノやヒトと濃厚に関わることで初めて「なぜ?」「どうして?」という好奇心が増幅する。この「なぜ?」を蓄積し、あるいは自分の知識や経験をフル動員して洞察する過程こそが旅であると感じるのである。
換言すれば「異質性こそ価値である」ことを知ることが旅の目的ではなかろうか。これから社会に出ていく若者たちは様々な知識や知恵を他人の経験を通じて学ぶことができる。ただし、それはこれから歳をとってもできることでもある。今は大学で学んだ知識を自分で体験することによって裏付け、新たな「なぜ?」を持ち帰り、また勉強するという作業をするに最適な環境にある。という思いが私のなかでは強いものだから、常に学生に対して熱く語りかけるのだが、これによって惹起される若者は多くない。
結局、私も若い頃というのは遠い外国や異文化への興味よりも身近なものへの関心が圧倒的に強い時期であった。大学3年生の時、生まれて初めてパスポートを取得し、スリランカへ出かけたのが最初の海外渡航であった。学生時代後半はそれこそアジアなどの外国を旅するために日本国内でアルバイトをするという状態だった。そして、アジアだけでなく、欧州、北米、中米などへ足を運んだ。これらの旅を通じて多様で異質な物事に圧倒され、魅せられた。その時に蓄積された「なぜ?」があまりに多く、これらの解は見つかったのかというと、次から次へと新しい「なぜ?」が舞い込んでくる始末である。
社会人となった今も幸運にもアジアと関わり続けている。これまでに蓄積した「なぜ?」は解を見つけたのだろうか。いや困ったことに、知れば知るほど分からなくなるといったスパイラルな現象が続いている。なぜ?という疑問がひとつ解けると、その向こうに複数のなぜ?が待ち受けているからである。
異質性との出会いを避けていれば解を求めて苦労することもない。「なぜ?」と洞察することはエネルギーを要する。ただし、このエネルギーは決して無駄ではないようだ。「異質性こそ価値である」という境地に立てば、「なぜ?」を洞察する過程で、今まで見えなかった日本が見えてくることがある。それは己を知ることでもある。これが本コラムのタイトルにもなっている「アジア目線」の含意でもあった。アジアから見る自分なのである。
アジアに限らずたくさんの見知らぬ土地で多様な「なぜ?」を拾い集めることが私にとっての旅であり、この洞察の旅は何やら自分探しの旅でもあり、まだまだ続くのである。
「人道の港 敦賀」から「現代のみなとまち」を再考する
シカゴ・マーカンタイル取引所の名誉会長で「金融先物取引の父」と呼ばれるレオ・メラメド氏(82)が、7月上旬に敦賀を訪れる。1940年にナチスの迫害から逃れるため、リトアニアの日本領事代理であった杉原千畝(ちうね)氏が発給した「命のビザ」を手に、ウラジオストクから敦賀港へ降りたって以来、実に74年ぶりのことである。
敦賀港が「人道の港」と呼ばれるようになったのは、こうした史実があったからにほかならないが、実は、当時の詳しい状況が明らかになったのは最近のことである。市内の歴史調査団体である日本海地誌調査研究会の井上脩代表が1998年頃から調査を始め、シンポジウム等の開催を経て2006年に本格的なプロジェクトチームが発足した。「リンゴを分けた」「銭湯を開放した」といった32件の新たな事実や彼らが残した腕時計などの現物が発見され、それらの結果は報告書や展示施設「人道の港 敦賀ムゼウム」で見ることができる。
今回、メラメド氏はムゼウムを訪問し、「お世話になった敦賀の人たちにお礼を言いたい」と話しているという(6月4日付福井新聞)。当時の状況を知るべくもない筆者にとっては展示を通じてしか述べることができないけれども、迫害から逃れて敦賀にやってきた人々と彼らを受け入れた敦賀市民には、いずれも忘れることのできない記憶であったのだろう。この記憶が記録となって現代に受け継がれ、共有されていることが氏の訪問につながったと言える。
このことから、「現代のみなとまち」とは何かをあらためて考えてみたい。戦後、交通体系の革新によって港湾はかつての姿から大きく変わった。船舶の大型化や荷役の機械化、コンテナ化等が進み、人々の移動手段も自動車や飛行機、新幹線などが主になったため、港湾は人々の日常生活から遠ざかっている。もはや人々の出会いや別れの場でもない。そのため、「みなとまち」として敦賀がどのように発展していくかを考えている筆者は、ややもすると鉄道や自動車が行き交う場所に「現代のみなとまち」を模索しがちとなっていた。もちろんそうした発想は重要であろう。しかし、港も依然として「心の交流」による人々の出会いの場であり続けていたのだ。メラメド氏の訪問は、かつての記憶と記録が今でも港に人々の出会いをもたらすことを示唆しているように思われる。
ほぼ時を同じくして、敦賀港に残る貴重な歴史文化資産「赤レンガ倉庫」の耐震改修工事と「ランプ小屋」の調査が始まっている。赤レンガ倉庫には巨大なジオラマが整備される予定で、鉄道ファンや子供にとって楽しい施設になるだろう。また、レストランなども併設され、若い層や女性にも魅力ある場所として再生されることが期待される。これはかつての物流拠点が集客を図るための観光施設に変わることを意味するが、当時の敦賀港の資料や記録が理解できるものになれば、内外との「心の交流」による人々の出会いの場がさらに増えることになる。こうした機能を加えていくこともまた「現代のみなとまち」に必要なことではないだろうか。タイの政治混乱とASEANシフト
昨年来、タイが政治的に混乱した状況が長期化し、今年初めにはインラック政権に反対する反政府勢力が、首都バンコクの主要道路をバリケードなどで封鎖するような事態になった。筆者が2014年3月上旬に現地を訪問した際には、幸運にも道路封鎖は解除の方向に向かっていた。しかし、かつて数々あった軍事クーデターとその解決のプロセスとは違い、その出口は以前よりはるかに遠いようだ。そして先日5月7日には、「神の声」と揶揄される憲法裁判所の判決によって、人事不当介入という理由でインラック首相は失職し、失職後もコメ担保融資問題で告発される見込みとなっている。5月20日には陸軍により戒厳令が発令され、5月22日にはついに8年ぶりのクーデターに発展した。陸軍の置かれた立場も微妙であり、この先さらなる混乱、衝突も予見される。
この20数年ほどのタイの政治を見ると、(1)タクシン(元首相)政権以前、(2)タクシン政権下、(3)タクシン亡命後、の3つの時期に分けられるだろう。タクシン以前の90年代では、軍事クーデターが頻発し、軍の戦車がバンコクを威圧する状況も見られた。しかし壮年期であったプミポン国王に対する国民の敬愛と求心力は圧倒的に強く、政治的危機も最終的には国王が調停者として乗りだして来ることを誰もが予想し、また期待した。これが2001年のタクシン首相の登場によって大きく変化する。タクシンの経済政策「タクシノミクス」は、良く言えば農村振興と農村部低所得者への手厚い支援、あるいはASEANを牽引するような外交政策などであった。反面、負の部分としてはバラマキ施策と強権、汚職、縁故主義などは、従来のタイの既得権益者、エスタブリッシュメントへの大胆な挑戦と受け取られ、そしてタイ王室を頂点とする保守的価値観を揺るがすような変化でもあったと考えられる。タクシンは2006年のクーデターによって国外追放されるが、その後の選挙によって実妹インラックが2011年首相についたことで、タクシンによる実質的な政権支配は続いている。タイ貢献党あるいはタクシン派は、農村部などの熱狂的とも言える支持によって総選挙には圧倒的な強さを誇っている。しかし昨年11月の恩赦法可決でタクシンの帰国を強引に可能にすることを政権が目指したため、今年2月におこなわれた総選挙では、反タクシン派による選挙ボイコットと妨害という異例の事態になった。タイ憲法裁判所は、この選挙を無効とする判決を下したことで、7月にはやり直し選挙を実施するとされているが実際におこなわれるかは不透明である。このような前代未聞の混乱において、従来のような国王による裁定は国王が高齢かつ病気療養中であることから難しい。また場合によっては皇太子への承継という事態も視野に入っている。
今ASEANシフトと言われる現象は、日系企業の中国からASEAN諸国への生産・販売活動の移動と捉えられている。しかしながらASEAN10カ国は個々に状況が異なっていることが特徴であり、全てのASEAN諸国に日系企業が等しく進出をし、また進出を検討しているわけではない。ASEAN各国においては、かつて多くの国で政治的な混乱とそれに伴う経済的な動揺を経験している。その中でタイは多くの点で安定しているということが、ASEAN諸国の中でも1980年代以降、日本からの直接投資がタイに集中したという理由の一つであると言われてきた。よく知られているように、現在では自動車産業を中心に巨大とも言える産業集積がタイに形成されている。しかし安定が不安に変わった時、企業がどのような投資活動をするかについては極めて不透明である。特に政治状況は移ろいやすく、また感情的にもなりやすい。今までのタイの経済的成功と日系企業はじめ外資にとって好ましいイメージを保てるかどうかは、現在の政治的な混乱をどう収拾するかにかかっているだろう。
環境政策からみた中国進出自動車メーカーの動向
今回は中国の環境政策に着眼して大手自動車メーカーの動向を紹介してみたい。この国の現在の環境政策は、従来のエンジン自動車よりも、ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、等のいわゆる環境対応車に転換して行こうとしている。エンジン自動車から電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)等にシフトする際に、自動車の部品調達の枠組みが大きく変わるのだから、大企業だけではなく、いわゆる部品サプライヤーである中堅・中小企業であっても、どの完成車メーカーがどの種類の環境対応車でイニシアティヴを取ろうとしているかに注意を払わなくてはならない。
(1)これまでの環境政策はどのようなものであったか。 中国の環境政策について、この間の勉強で最も参考になった著作の一つは中西孝樹氏の『トヨタ対フォルクスワーゲン(VW)―2020年の覇者をめざす最強企業―』(日本経済新聞社、2013年)である。詳しい紹介はできないが、環境政策に限った場合、その要点は次のように整理できる。
従来型エンジン自動車:中国市場に限っていえば、ドイツ・フォルクスワーゲン(VW)が14.9%と販売シェアのトップを走るため(2013年の販売実績)、当面、欧州勢が強みとする「従来型エンジン自動車を改良したもの」(ディーゼルエンジン車や直噴小排気量過給エンジン車)がそのまま普及する可能性が高い。しかし、中国政府は大気汚染対策の1つの柱として新エネルギー車優遇政策(新エネ政策)を推し進めており、中長期的には、従来型エンジン自動車が残るとしても、その市場規模(販売台数)は縮小する方向である。この新エネ政策はプラグインハイブリッド車(PHV)と電気自動車(EV)、ならびに燃料電池車に限り消費者向けの補助金を出すというものである。例えばEVは最大94万円、PHVは55万円の補助金が支払われるという。中国政府は、この新エネ政策により2020年までにEVとPHVを累計で500万台普及させる計画であるという(『日本経済新聞』2014年4月19日付)。 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV):しかし、こうした優遇措置にもかかわらず、これまでのところEVとPHVの2013年の年間販売台数は全体の1%以下(0.8%)にとどまっている。特にEVの普及が難しい理由の一つは「一回の充電で走行可能な距離がハイブリッド車(HV)と比べて短いこと」である。もう一つの理由は「充電インフラの未整備」である。とりわけ国土が「広大な中国ではEVだけでは(エコカーの普及は)成り立たない」との指摘もあるという(福井新聞2014年4月23日付)。 ハイブリッド車(HV):ではトヨタやホンダなど日本勢が強みを持つハイブリッド車(HV)はどうか。現行の環境政策ではHVは、新エネ車ではなく、省エネ車として位置付けられており、消費者向けの補助金対象から除外されていること、また、尖閣列島問題をはじめ、日中間の歴史や政治の問題にまつわる反日感情が存在すること、等が影響して、2013年の年間販売台数全体の数%にとどまっている。なお、2013年時点で中国市場における日本のビッグスリー各社の販売シェア(HV以外も含む)はそれぞれ、日産5.7%、トヨタ4.1%、ホンダ3.4%である(『日本経済新聞』2014年4月19日付)。
以上を要するに、これまでの新エネ政策、すなわち電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド車(PHV)重視の政策は、今のところ上手くいっていないということである。(2)環境政策の新しい動きはどうなっているのか。 現下の環境政策はこのように期待どおりの効果を出せていないが、国内外から早急に大気汚染対策を講じるように求められている中国政府にとっては、放置しておける問題ではない。そこで、ここ数週間の新聞報道によれば、中国政府(具体的には経済政策担当大臣である馬凱副首相)は次のような政策転換を図ろうとしている。これまで電気自動車(EV)など充電可能な環境対応車に限られてきた消費者向け補助の対象を、早くも2015年にハイブリッド車(HV)にまで広げるというものである。まだ検討段階であるとされるが、仮に導入されることになれば、1台当たり約25万円(現地生産車に限り適用される)の補助金が支払われるようになるという。新聞は、HVに強みを持つトヨタとホンダなどの日本勢には追い風になると、積極的に評価している。トヨタは2015年をめどに電池、モーター、インバーターなどのHV用基幹部品の現地開発・生産を、ホンダは2016年からHV車両の現地生産を予定するなど、一層の現地化を推し進めようとしている。中国市場で劣勢に立たされてきた日本勢がここに来てようやく攻勢をかけ始めた(『日本経済新聞』2014年4月19日、4月21日付)。