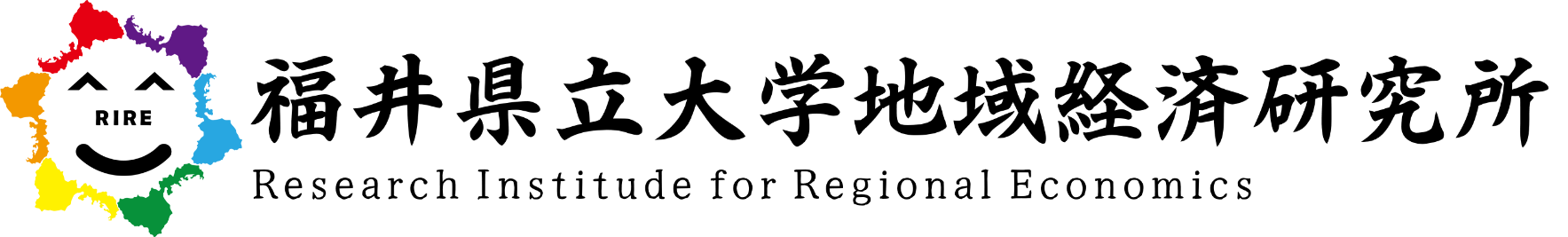2015年3月
「北前船主の館 右近家」を訪ねて
先日、越前海岸の南端、敦賀湾の入り口に位置する旧河野村(福井県南条郡南越前町河野)を訪ねた。当地には、江戸時代から明治時代にかけ北前五大船主として名を馳せた「北前船主の館 右近家」がある。そもそも北前船とは何か。蝦夷地と大阪を西回り航路(日本海航路)で結び、船主自らが立ち寄る港々で商品を買い付けながら、それら商品を別の港で販売し利益を上げる買積み廻船のことを言うらしい。
ところで、江戸時代、武士の給料は米を単位として与えられていたが、北海道の松前藩では米が取れないため、家臣には漁場が与えられた。家臣は、自分の漁場で取れた漁獲物を本州の商人に売り、生計を立てていたが、商いに熟れない家臣たちは商人に漁場での商売を任せ、商人から運上金を取り生計を立てるようになった。そこでできた制度に場所請負制というものがある。これは、松前藩の家臣が自分の漁場での商いを商人に任せた特権制度であり、場所請負人とは特権を与えられ運上金を収めた商人のことを指す。江戸前期から江戸中期まで場所請負人の特権を握った近江商人は蝦夷地の産物を荷所船に乗せて敦賀や小浜の港に運んだ。この荷所船の船頭として越前や加賀の船乗りたちが雇われていたのである。しかし、江戸時代中ごろになると、蝦夷地に進出してきた江戸商人によって近江商人が衰退していく。この近江商人の衰退により、荷所船の船頭をしていた越前や加賀の船乗りたちは、これまでの経験を活かして、自分で船を持ち買積みという商いを始めるようになったのである。これが北前船の始まりとも言われる。各地を寄港しながら自分で安く商品を仕入れ、高く売れる港で売却する北前船の買積みという商い方法は、運賃積と異なり大きな利益を生み、主に西回り航路で蝦夷と大阪を結ぶ北前船の時代は明治の中頃まで続いたという。
では、北前船は何を運んでいたのか。大阪から蝦夷地に向かう荷を下り荷と呼び、大阪や下関の港では、竹、塩、油、砂糖、木綿、紙、たばこなどの日用雑貨を、小浜や敦賀の港では、縄、むしろ、蝋燭など、新潟や坂田の港では米などを積み込んだという。逆に、蝦夷地から大阪に向かう荷を上り荷と言い、カズノコ、コンブなどの海産物やニシンを積み込んだ。北前船の一航海の利益は、下り荷と上り荷を合せた収益から、船乗りの給料、食費、船の修理代を差し引いたものであった。明治5年の「八幡丸」の収支報告を見ると、収入は下り荷が223両、上り荷が1,169両、その他146両、合計1,538両。支出は724両で、差し引き814両の利益が出ている。こうしてみると、上り荷の利益が極めて大きいことがわかる。当時、蝦夷地で取れたニシンは田や畑の肥料として大量に使用されていた。千石船一航海1000両と呼ばれた北前船の収益の多くは、上り船のニシンだったのである。
さて、話を右近家に戻そう。旧河野村にある右近家は、いったい何時頃誕生したのであろう。一説によれば、初代、右近権左衛門が一軒の家と一槽の船を持ち、船主として名乗りを上げたのが延宝8年(1680年)の頃と言われる。その後、右近家の廻船経営が明らかとなるのは、江戸時代の中頃、天明年間(1781から1789年)、7代目権左衛門の頃からである。7代目は蝦夷地と敦賀・小浜等を往復し物資を運ぶ近江商人の荷所船の船頭をする傍ら、自分で物資を売買する買積み商いを始め、次第に北前船主としての道を歩み出したのであった。こうして北前船の基礎を築いた8代目、繁栄を極めた9代目と続いていく。10代目は、明治時代中頃から衰退していく北前船主の中でいち早く汽船を導入し輸送の近代化をはかる一方、海上保険会社の創立など事業の転換をはかった。11代目は、日本海上保険会社と日本火災保険株式会社の合併や右近商事株式会社など経営の基盤を確立した。そして、12代目、安太郎氏は右近家の歴史と伝統を受け継ぎ日本火災海上保険株式会社の社長を長く務める一方、旧河野村の北前船歴史村事業に賛同し、本宅を村の管理にゆだね「北前船主の館 右近家」として一般に公開し、現在に至っている。
いずれにせよ、北前船の船主が当地に存在していたという事実は、15から16世紀、あのコロンブスやマゼランが活躍した大航海時代を彷彿させるものであり、さらに、小浜、敦賀、三国など大陸文化伝来の玄関口として栄えた地が存在していた事実と合わせて考えれば、福井県そのものが古より広域ネットワークの拠点として、経済、文化、人的交流等の面で極めて重要なポジションを担っていた事実を認めなければならない。ふくい地域経済研究第20号