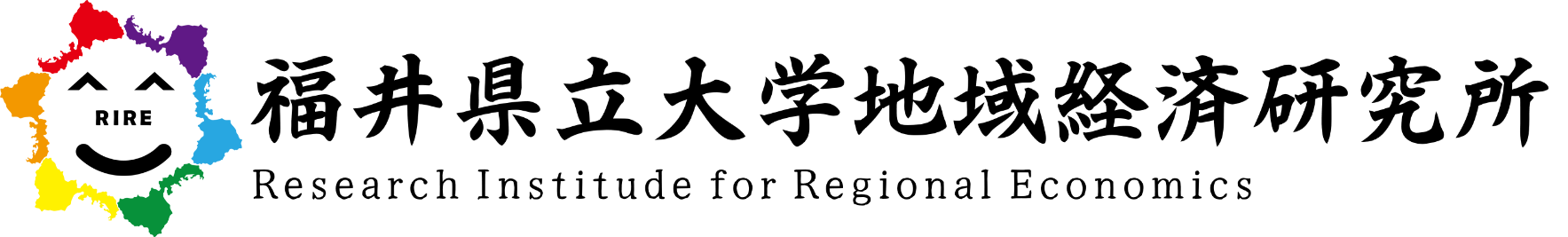2016年7月
格差社会と内田惣右衛門の救貧活動が示唆するもの
2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震と、日本では短期間で大災害が連続して発生した。多くの被害が出ており、困難な状況が続いているものの、活発なボランティア活動や寄付活動からは復興の兆しを垣間見ることもできる。こうした災害時において、著名人が個人資産から義捐金や支援金を寄付し、さらにその金額を公表するという行動が見られた。東日本大震災後にソフトバンクの孫氏が100億円を寄付したことは驚きであったし、ユニクロの柳井氏、楽天の三木谷氏も10億円の寄付をしている。多大な貢献として喜ばれる面がある一方で、いともたやすく巨額な寄付ができる資産所有に、あらためて格差社会の一面が浮き彫りになったともいえるだろう。
欧米諸国には「ノーブリス・オブリージュ」という理念があり、富裕層の義務として貧困層に寄付や支援を行うということが習慣や伝統として根付いている。実は日本でもかつては富者の寄付や社会貢献活動が行われており、しかも、名を伏せて秘かに「喜捨」するという方法で、さらに「善行」として行われていた。その代表として名前が挙がるのが、三国の豪商、内田惣右衛門である。
内田家は江戸時代に北前船の海運業で福井藩を潤した三国の代表的な廻船問屋であり、飢饉のたびに出費をして町の窮民救済に協力した三国の豪商の中で最大の功労者であるとされる。こうした救済活動によって三国では、全国的に米騒動の暴動が広がり、近隣地域が騒然たる無政府状態になった時にも暴動が起こらなかった。内田家が行った救貧活動は、飢饉による困窮者への施与だけでなく、火事見舞いや病気見舞い、未亡人や高齢者・病人のいる家庭への援助等があり、妻を失った人や行旅病人のような行き倒れの人も救済している。こうした救貧活動に身をささげるようになった惣右衛門の生き方の基盤として最も大きな思想は、人類平等の思想や人間観であり、確固たる人格尊重の人権意識がこのような実践の基盤にあったと考えられている。東尋坊のほど近くに内田惣右衛門記念館が建っているが、華美を嫌う惣右衛門の意を重んじて、現在の当主によって残念ながら閉館となっている。
資本主義社会で生きる私たちは、失業、収入喪失、貧困といったリスクを抱えている。そうしたリスクに対応し、最低限の生活を送れるように様々な社会保障制度が築かれてきた。しかし、その所得配分機能が十分には機能しておらず、多くの先進諸国において持つ者と持たざる者との間に大きな生活水準の格差が生じており、約1%の大富豪が95%以上の富を独占する状況が生まれている。こうした状況を踏まえると、現代社会においても富裕層により多くの救貧活動を期待してもよいのではないだろうか。日本にもかつて内田惣右衛門のような豪商がいたということは示唆に富んでいるように思われる。
(本稿の執筆では、元福井県大教授の大塩まゆみ氏の著書である「「陰徳の豪商」の窮民思想―江戸時代のフィランソロピー―」(ミネルヴァ書房)を参考にさせていただいた。)