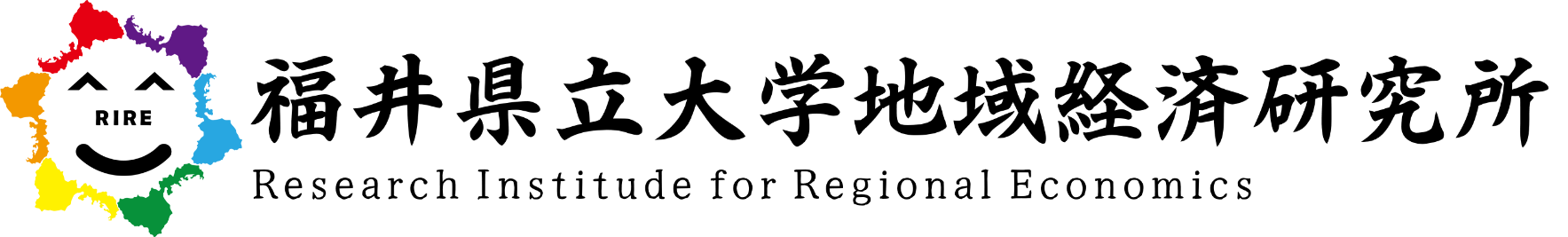2015年6月
人口からみた選挙制度と年齢
諸制度には適応される対象年齢が定められているものが多い。
6月17日に18歳以上に選挙権を与える改正公職選挙法が成立した。安全保障関連法案の議論に隠れてあっさりと可決された感がある。経過はさておき、これによって来夏の参院選では、日本の歴史上初めて18、19歳の未成年者が国政選挙で投票することになる。
来年の18、19歳人口はあわせて約240万人。日本のような先進国では乳幼児ならびに若者の死亡率は低い。さらに、国際人口移動が相対的に少ないわが国では、出生時の人口と数年後、十数年後、少なくとも成人期までの当該年齢人口が概ね一致する。よって、今から17、18年前の出生数(1997年119万人、98年120万人)をみれば、将来人口推計など難しそうなことをしなくても、制度変更によって影響を受ける人口の概数くらいは誰にでも見当がつく。
ただし、地域別には状況が異なる。死亡率には全国的にさほど大きな地域差がないものの、選挙区間を跨ぐ人口移動は激しい。とりわけ大学進学時に移動する若者が多いことは皆さんもお気づきであろう。今日の日本の若者は男女とも半数が大学に行く。地元の高校生が卒業後に域内の大学に行くのか、域外の大学に行くのかによって、地域の人口は大きく変わる。当然のことながら、新たに選挙権を得る18、19歳人口が多い地域と少ない地域が出てくる。大学数の最も多い首都圏、福井県からも近い京都や大阪の大学には全国から多くの若者が集まる。単純に考えれば、今回の選挙制度の変更によって、”一票の格差”はこれまで以上に広がることになる。今回の制度変更は”一票の格差”是正を目的としたものではないことが分かる。では何が目的なのであろう?
人口の年齢構成からすると高齢化が進むにつれて選挙権を持つ人口(現行20歳以上人口)に占める高年齢者の割合が高くなり、若者の声が政治に反映され難くなっていることへの対応とみる向きもあるが、今後18、19歳の新たな参入によって投票状況を含めた選挙の在り方が変わるのか否か、今後の実績をしっかりと検証し見極める必要がある。
ちなみに、選挙権は選挙人名簿に登録されている地域で与えられる。所管官庁の総務省のHPでは、”選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満20歳以上(※これが今回18歳以上に変更される)の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です”と書かれている。要するに、住民票を異動させなければ、域外の大学所在地で生活していたとしてもそこで投票する資格は無い。逆に言えば、投票したい地域に住民票を残しておけばそこに住んでいる実態がなくても投票ができる。なお細かいことを言えば、住民票の異動後3か月以上経っていなければ選挙人名簿に載らないので、来夏の参院選がいつ行われるか、いつ住民票を移すかによって、当地の選挙権が得られるか否かが決まる。
選挙法が改正された日の夕刻NHKの福井県版ニュースを観ていると、福井県知事の西川氏が”ふるさと投票”と言っておられた。福井県外で進学したり就職したりしても生まれ故郷の政治や行政に関心を持ち続ける若者が増えることはとても大切だと思う。”ふるさと納税”同様、地域社会を支えるツールの一つに繋がれば望ましいと考える。余談だが、上述のNHKのニュースでは的外れなコメントがされていた。確か、福井県においては住民票登録人口よりも戸籍簿に登録されている人口が多いので、”ふるさと投票”の知事のアイデアは今後18、19歳の若者の地元関心を高める妙案である、とか。個人の戸籍がどこに置かれているのかと選挙制度とは全く関係がないので、何を言おうとしているのか私にはよく分からなかった。
ちなみに、議員定数は5年に一回行われる国勢調査の結果をもとに更新される。今年の数か月後の10月1日が調査日だ。ただ、国勢調査は現住地で国民の状況を把握するもので、住民登録とは直結していない。選挙で選ぶものと選ばれるものの人数が異質の人口統計をもとに決められている。今回の公職選挙法の変更を機に若者の投票への関心についての議論が盛んに行われているようであるが、わが国の選挙制度には私たち”大人”がまずしっかりと考えなければならない課題が少なくないように思う。
現地化について考えること
およそ過去30年、日本からアジアに進出する日本企業(製造業)は海外子会社で管理職を担う幹部人材の「現地化」が遅れていると批判されてきた。しかし、現時点でもなお現地人をマネジメント層に登用するという動きはあまり進展がみられない。この「現地化」という言葉は、その含意として「日本人中心の経営の弊害」、「現地人への事業運営の移管」、「日本人ゼロ」、「現地人の経営参加」といった事柄がイメージされる。しかし、現地化を推進することのリスクも決して小さくない。しかし、国内外の研究者の多くはそのリスクを過小評価し、「日本人中心の経営の弊害」ばかりを指摘してきた。
ここで言う「日本人中心の経営の弊害」とは、海外子会社の主要な意思決定のポストに現地駐在の日本人スタッフがつくために現地人の「モチベーション」が停滞するとか、有能な現地人の「確保・定着」が困難になるとか、あるいは、給与水準の高い日本人スタッフに頼った事業運営は「日本本社側のコスト」の増大につながるとか、「現地適応する」にも敏感に現地の市場ニーズをキャッチできないとか、様々な問題を意味している。
いずれも「日本人中心の経営」特有の問題であるが、逆に、「過度の現地化」(=日本人スタッフを減らしすぎること)にも次のようなリスクが潜んでいるのも事実である。海外子会社がグローバルな視点を持つことが難しくなること、日本人に海外経験を積ませることが難しくなること、日本本社が海外子会社をコントロールすることが難しくなること等がそれである。
つまり、日本の進出企業がマネジメント層の現地化を考える際、「日本人中心の経営の弊害」と「過度の現地化」に潜伏するリスクの両面を勘案する必要があるということである。
この課題に対して日本の進出企業はどのようにして対処しているのか。一例であるが、インドに現地子会社を持つ日系自動車部品メーカーでは、当該子会社の経営トップが「現地人」であり、「労務管理」、「営業」を担当している。それ以外の「技術・品質面と資金面の管理」は「日本人スタッフ」が責任をもつ。つまり、経営トップは「現地人」であるが、同社の場合、管理項目の主要な柱である、品質、財務面については「日本人スタッフ」に責任を持たせることで、海外子会社が本社の意向を無視して独走することに対して一定の歯止めの管理を行っている。したがって、経営トップが「現地人」であると言っても字義通り「現地人」が海外子会社の管理を行う完全な権限を持っているわけではなく、一定の管理権限は「日本人スタッフ」が握っているのである。
このように、「現地化」という言葉は聞こえがよく、「日本人中心の経営の弊害」を意識させ、現地人に経営を任せればうまく行くという考え方の普及に寄与した。しかし、実態は日本人スタッフが担っている高いポジションを現地人に全面的に任せる例はあまりみられない。現下の日本の進出企業の本音をあえて言えば、「経営が上手く行けば、現地人であろうが日本人であろうが、誰が経営しようが、たいした問題ではない」。現地化というよりも、経営管理をしっかりして着実に利益を上げることのほうに注力するという状態が続いているのである。