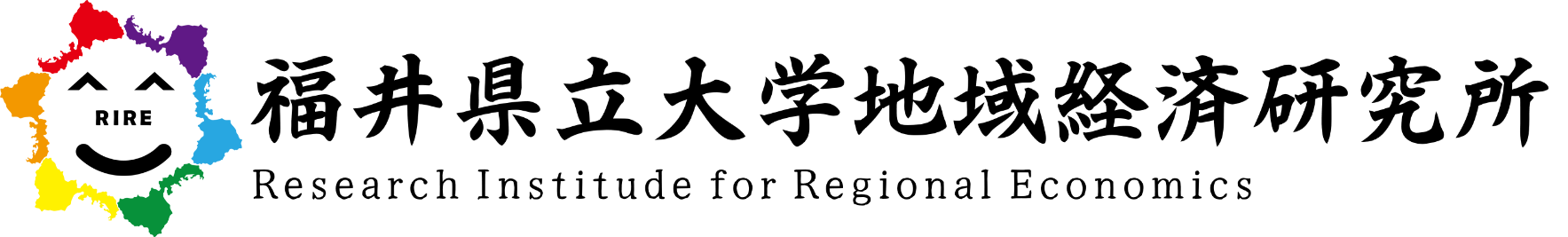2016年4月
「パナマ文書」の衝撃
一般的に、日本人の多くは税金を「納める」というよりも「取られる」と感じているらしいが、「取られたくない」気持ちは世界共通であるようだ。いわゆる「パナマ文書」で明らかにされた、主要各国の多数に及ぶ政治家や関係者が「タックス・ヘイブン」を利用していた問題のことである。
OECD租税委員会の報告(2000年)によると、タックス・ヘイブンとみなされる国は問題の発覚したパナマだけでなく、カリブ地域や太平洋地域を中心に35か国にも及ぶという。これまで、タックス・ヘイブンの問題は、グローバルに活動する大企業が、およそ実態のない会社をパナマなどのほとんど税金を課されない国に設立し、世界各国で多額の利益をあげながら、それに見合うだけの納税をしていなかったことが注目されてきた。しかも、タックス・ヘイブンでは情報開示がほとんど行われず、全容を把握することはきわめて困難である。このことについて「税逃れ」と批判さるべきは言うまでもないが、志賀櫻著「タックス・ヘイブン」(岩波新書)などを読むと、「逃げる税金」と「捉える国家」の双方に膨大な人材と知恵が投入されていることに「もっと有益な使い方はないのか」と虚無感さえ覚えてしまう。
今回報道されたパナマ文書は、法律事務所「モサック・フォンセカ社」による、約40年間に及ぶ1150万件の文書である。匿名で南ドイツ新聞が入手した後、国際調査報道ジャーナリスト連合ICIJで分析されているという。報道の中で特に注目されているのは、多くの政治家やその関係者もまた企業と同様にタックス・ヘイブンを利用していたことである。これが企業と同様の税逃れであることはもちろん問題だが、より深刻なのは「税金を使う立場にある政治家が租税を回避していた」ということではないだろうか。税金は彼らの意思決定の下で様々な公共サービスを行うための財源であり、それを彼ら自身が「納める」ことなく「取られたくない」と考えてタックス・ヘイブンを利用したのであれば、政治家の存在意義にも関わる可能性がある。今回の件で問題視されるのは、この点であろう。
タックス・ヘイブンの利用は企業や政治家に限られるわけではないが、実態は大半の中間層や低所得者層が利用することなく各国の制度に従って納税している。こうしたなかで、パナマ文書は「公共サービスの価値が政治家自身に十分自覚されていない以上、すべての人にそう思われても仕方がない」という認識を拡散してしまう可能性がある。パナマ文書の衝撃は、政治家の辞任などに広がることが懸念されているが、私たちにも納税義務の意識後退という危険性を孕んでいるような気がしてならない。