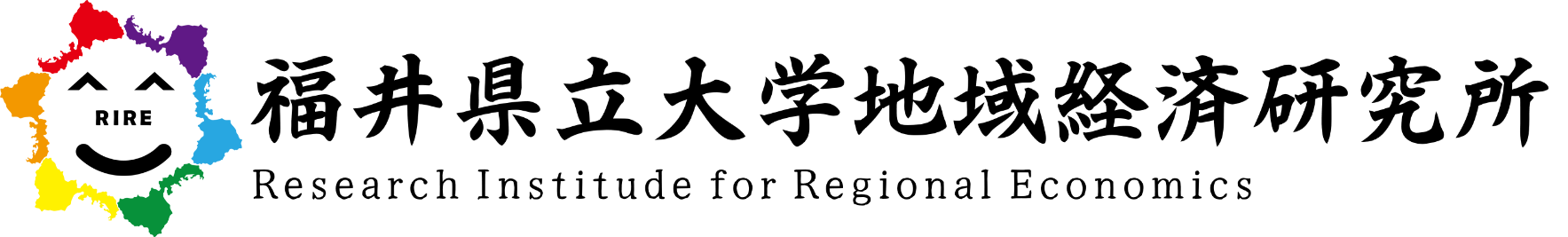環境政策からみた中国進出自動車メーカーの動向
今回は中国の環境政策に着眼して大手自動車メーカーの動向を紹介してみたい。この国の現在の環境政策は、従来のエンジン自動車よりも、ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、等のいわゆる環境対応車に転換して行こうとしている。エンジン自動車から電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)等にシフトする際に、自動車の部品調達の枠組みが大きく変わるのだから、大企業だけではなく、いわゆる部品サプライヤーである中堅・中小企業であっても、どの完成車メーカーがどの種類の環境対応車でイニシアティヴを取ろうとしているかに注意を払わなくてはならない。
(1)これまでの環境政策はどのようなものであったか。 中国の環境政策について、この間の勉強で最も参考になった著作の一つは中西孝樹氏の『トヨタ対フォルクスワーゲン(VW)―2020年の覇者をめざす最強企業―』(日本経済新聞社、2013年)である。詳しい紹介はできないが、環境政策に限った場合、その要点は次のように整理できる。
従来型エンジン自動車:中国市場に限っていえば、ドイツ・フォルクスワーゲン(VW)が14.9%と販売シェアのトップを走るため(2013年の販売実績)、当面、欧州勢が強みとする「従来型エンジン自動車を改良したもの」(ディーゼルエンジン車や直噴小排気量過給エンジン車)がそのまま普及する可能性が高い。しかし、中国政府は大気汚染対策の1つの柱として新エネルギー車優遇政策(新エネ政策)を推し進めており、中長期的には、従来型エンジン自動車が残るとしても、その市場規模(販売台数)は縮小する方向である。この新エネ政策はプラグインハイブリッド車(PHV)と電気自動車(EV)、ならびに燃料電池車に限り消費者向けの補助金を出すというものである。例えばEVは最大94万円、PHVは55万円の補助金が支払われるという。中国政府は、この新エネ政策により2020年までにEVとPHVを累計で500万台普及させる計画であるという(『日本経済新聞』2014年4月19日付)。 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV):しかし、こうした優遇措置にもかかわらず、これまでのところEVとPHVの2013年の年間販売台数は全体の1%以下(0.8%)にとどまっている。特にEVの普及が難しい理由の一つは「一回の充電で走行可能な距離がハイブリッド車(HV)と比べて短いこと」である。もう一つの理由は「充電インフラの未整備」である。とりわけ国土が「広大な中国ではEVだけでは(エコカーの普及は)成り立たない」との指摘もあるという(福井新聞2014年4月23日付)。 ハイブリッド車(HV):ではトヨタやホンダなど日本勢が強みを持つハイブリッド車(HV)はどうか。現行の環境政策ではHVは、新エネ車ではなく、省エネ車として位置付けられており、消費者向けの補助金対象から除外されていること、また、尖閣列島問題をはじめ、日中間の歴史や政治の問題にまつわる反日感情が存在すること、等が影響して、2013年の年間販売台数全体の数%にとどまっている。なお、2013年時点で中国市場における日本のビッグスリー各社の販売シェア(HV以外も含む)はそれぞれ、日産5.7%、トヨタ4.1%、ホンダ3.4%である(『日本経済新聞』2014年4月19日付)。
以上を要するに、これまでの新エネ政策、すなわち電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド車(PHV)重視の政策は、今のところ上手くいっていないということである。
(2)環境政策の新しい動きはどうなっているのか。 現下の環境政策はこのように期待どおりの効果を出せていないが、国内外から早急に大気汚染対策を講じるように求められている中国政府にとっては、放置しておける問題ではない。そこで、ここ数週間の新聞報道によれば、中国政府(具体的には経済政策担当大臣である馬凱副首相)は次のような政策転換を図ろうとしている。これまで電気自動車(EV)など充電可能な環境対応車に限られてきた消費者向け補助の対象を、早くも2015年にハイブリッド車(HV)にまで広げるというものである。まだ検討段階であるとされるが、仮に導入されることになれば、1台当たり約25万円(現地生産車に限り適用される)の補助金が支払われるようになるという。新聞は、HVに強みを持つトヨタとホンダなどの日本勢には追い風になると、積極的に評価している。トヨタは2015年をめどに電池、モーター、インバーターなどのHV用基幹部品の現地開発・生産を、ホンダは2016年からHV車両の現地生産を予定するなど、一層の現地化を推し進めようとしている。中国市場で劣勢に立たされてきた日本勢がここに来てようやく攻勢をかけ始めた(『日本経済新聞』2014年4月19日、4月21日付)。