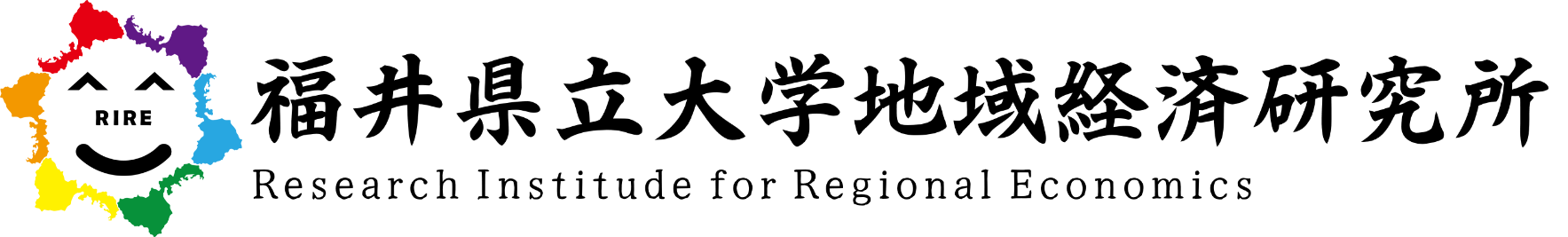「人道の港 敦賀」から「現代のみなとまち」を再考する
シカゴ・マーカンタイル取引所の名誉会長で「金融先物取引の父」と呼ばれるレオ・メラメド氏(82)が、7月上旬に敦賀を訪れる。1940年にナチスの迫害から逃れるため、リトアニアの日本領事代理であった杉原千畝(ちうね)氏が発給した「命のビザ」を手に、ウラジオストクから敦賀港へ降りたって以来、実に74年ぶりのことである。
敦賀港が「人道の港」と呼ばれるようになったのは、こうした史実があったからにほかならないが、実は、当時の詳しい状況が明らかになったのは最近のことである。市内の歴史調査団体である日本海地誌調査研究会の井上脩代表が1998年頃から調査を始め、シンポジウム等の開催を経て2006年に本格的なプロジェクトチームが発足した。「リンゴを分けた」「銭湯を開放した」といった32件の新たな事実や彼らが残した腕時計などの現物が発見され、それらの結果は報告書や展示施設「人道の港 敦賀ムゼウム」で見ることができる。
今回、メラメド氏はムゼウムを訪問し、「お世話になった敦賀の人たちにお礼を言いたい」と話しているという(6月4日付福井新聞)。当時の状況を知るべくもない筆者にとっては展示を通じてしか述べることができないけれども、迫害から逃れて敦賀にやってきた人々と彼らを受け入れた敦賀市民には、いずれも忘れることのできない記憶であったのだろう。この記憶が記録となって現代に受け継がれ、共有されていることが氏の訪問につながったと言える。
このことから、「現代のみなとまち」とは何かをあらためて考えてみたい。戦後、交通体系の革新によって港湾はかつての姿から大きく変わった。船舶の大型化や荷役の機械化、コンテナ化等が進み、人々の移動手段も自動車や飛行機、新幹線などが主になったため、港湾は人々の日常生活から遠ざかっている。もはや人々の出会いや別れの場でもない。そのため、「みなとまち」として敦賀がどのように発展していくかを考えている筆者は、ややもすると鉄道や自動車が行き交う場所に「現代のみなとまち」を模索しがちとなっていた。もちろんそうした発想は重要であろう。しかし、港も依然として「心の交流」による人々の出会いの場であり続けていたのだ。メラメド氏の訪問は、かつての記憶と記録が今でも港に人々の出会いをもたらすことを示唆しているように思われる。
ほぼ時を同じくして、敦賀港に残る貴重な歴史文化資産「赤レンガ倉庫」の耐震改修工事と「ランプ小屋」の調査が始まっている。赤レンガ倉庫には巨大なジオラマが整備される予定で、鉄道ファンや子供にとって楽しい施設になるだろう。また、レストランなども併設され、若い層や女性にも魅力ある場所として再生されることが期待される。これはかつての物流拠点が集客を図るための観光施設に変わることを意味するが、当時の敦賀港の資料や記録が理解できるものになれば、内外との「心の交流」による人々の出会いの場がさらに増えることになる。こうした機能を加えていくこともまた「現代のみなとまち」に必要なことではないだろうか。