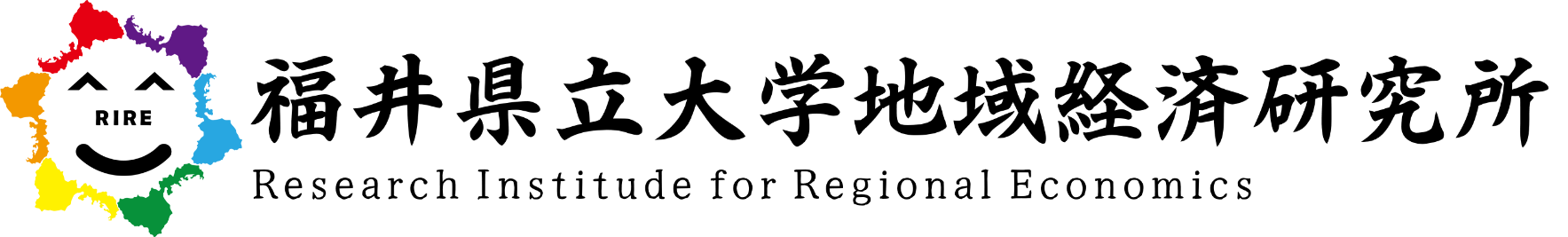動物行動学・仏教・言語批判哲学
ウィトゲンシュタイン(オーストリア1889-1951)の言語批判哲学を研究している。まったく関係なさそうな二つのところから言語批判哲学に繋がったので、ご紹介したい。
一つ目は、ドイツの動物行動学者のユクスキュル(1864-1944)が考えた「環世界(Umwelt)」という概念。生物はみんな同じように世界を見ているわけじゃない。感覚器官は生物種ごとに性能が異なっている。だから同じ世界の住人でも、生物種ごとに捉えている世界は違っている、生物種ごとに「環世界」が異なっている、とユクスキュルは主張する。つまり知覚内容は感覚器官の性能と相対的に決まることになる。例えば、人間の耳は、20~20.000ヘルツの空気の粗密波しか音として聞くことができない。しかし犬の耳はもっと高い周波数の粗密波を音として聞くことができる。だから周りの人間には気付かれずに、犬に指示を出すことのできる犬笛というものがある。また、光の三原色は赤・緑・青だが、赤(700ナノメートル)・緑(546.1ナノメートル)・青(435.8ナノメートル)の3種類の電磁波だ。つまり光の三原色は自然そのものの性質ではなく、また光の三原色はこの3種の電磁波がもつ性質でもない。人間の眼がこの3つの波長の電磁波に生理化学的反応を起こしているだけだ。世界が見えているように見えるのは、世界そのものがそうだからではなくて、人間の眼の性能によってそう見えているのである。
同じことが知性にも言えないだろうか。私たちは知識とは世界そのものを知ることだと思っているが、私たちの感覚に限界や制限があるように、私たちの知性にも限界や制限があるのではないか。例えば脳の構造上の限界や制限を考えることもできるが、ここでは言語を考える。それは、知性の働きの結果が知識であり、知識の表現が言語だからだ。しかし、言葉は世界を客観的に表現することができるのだろうか。言葉の上では、何にでも「それは、なぜ? どうして?」と問えるが、物事には必ず原因があるのだろうか。因果関係は世界の見方の一つに過ぎないのではないか。そもそも、主語・述語という文法は世界自体の構造なのだろうか。いや、知識や言語は私たちがより便利に生活するための、よりうまく欲望を満たすための道具ではないか。
もう一つは仏教。仏教の目的はシンプルで、苦が生じるメカニズムを明らかにして、苦を消滅させることにある。そして仏教の世界観は、無常・無我に尽きる。無常とは常なるものは何もない、あらゆるものは時とともに変化し移ろい行く。そして、無我とは人間の自我ばかりではなく、あらゆるものに自性、つまり常なる本質がないということ。
では、苦の生じるメカニズムとは。この世が無常・無我であることを知らないこと、これを「無明」という。この無明に縁って、煩悩が生じ、この煩悩が満たされないことによって苦が生じる、というものだ。では、苦を消滅させるには。一つは煩悩を満たしまくること。しかしこれはできない。苦の典型は老・病・死だが、これらを回避する術はない。もう一つは、この世が無常・無我であることをよくよく知って、無明を解消して、それによって煩悩を生じなくさせて、苦を生じなくさせるという仕方だ。こちらが仏の教えに他ならない。
逆に常なるものがないと成立しないのが「分別」である。分別の基礎は分けて区別することにある。しかし分けられ・区別される物事を安定しているもの、つまり常なるものと看做さなくては、分けようも、区別しようもない。そして、分別するということは、物事を区別すること、分節化すること、概念化すること、そして言葉で表現すること、要は物事に対して知性を使って対処することである。そして分別こそが無明の証に他ならない。したがって、仏教はこの人間の知性を疑う。ここに仏教の知識批判・言語批判がある。悟りの智慧は、まさに「無分別」智なのだ。