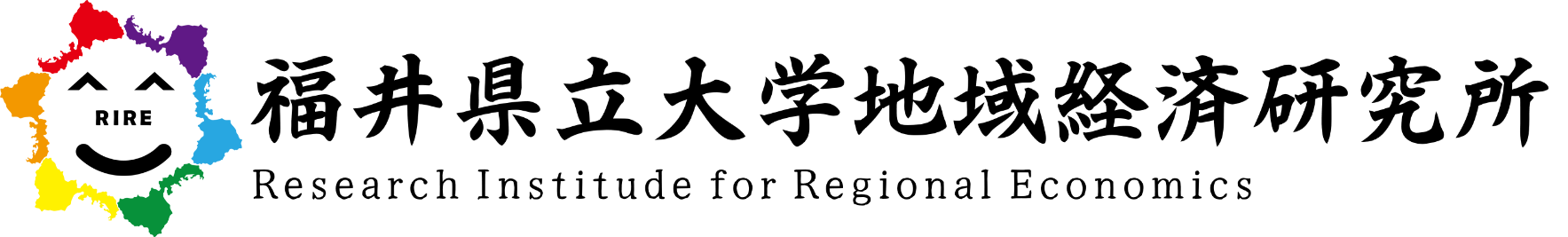2021年
地域産業の高度化を目指して
福井県の産業構造を眺めてみると、その特徴は、製造業と建設業に特化した地域であることと、その中で、製造業は、繊維産業や眼鏡枠産業、伝統的工芸品産業などを中心に多様な産業で付加価値生産性が低いといった特徴がある。そのため、福井県の産業界では、これまで各産業の高付加価値化を目指して、技術・製品開発、流通の簡素化、販路開拓など多様な試みを実践してきたことは言うに及ばない。
話は変わるが、フランスの経済学者・思想家のジャック・アタリは、2009年の著書「危機とサバイバル」の中でパンデミックの発生を予測し、今回の新型コロナウイルス感染症が、1929年の世界恐慌、2008年のリーマンショックよりも甚大な被害を及ぼすことを示した。そして、これを回避するために、世界の経済を全く新しい方向に設定しなおす必要性があることを述べている。具体的には、世界は爆弾や武器ではなく医療機器や病院、住宅、水、良質な食糧などの生産を長期的に行うべきであり、そのためには多くの産業で大規模な転換が求められることを示唆している。すなわち、人類が生きるために必要な食糧、医療、教育、文化、情報、イノベーションなどの提供を意識した産業、生きるために本当に必要なものの生産に集中することこそが今求められているということであろう。
ちなみに、コロナ禍における地域産業の生産活動に着目すると、例えば、福井県立大学が年末に実施した企業調査(福井県企業の「コロナ禍での事業活動に関する緊急調査」)では、アンケートに回答した企業521社の約2割の企業でウイルスや自然災害などから身を守る新製品・サービスの開発が行われていることがわかった。それは、まさに地域企業の間で「命を守る産業分野」への挑戦が始まったということではないだろうか。「命を守る産業分野」とは、今回のコロナ感染症だけでなく自然災害など人間に危険を及ぼす現象の発生を予測し、間接、直接的に人の身体を守る製品開発・サービス開発を行う分野を指す。例えば、農産物・食品加工分野でいえばクオリティーの高い作物や食品加工物の生産、製造業の分野ではウイルスをシャットアウトする住宅部材の生産や身を守るフェイスシールド、防護服・マスクなどの生産、医療行為、ドローンを使った監視システムなどの研究・開発を行う産業分野を指す。それは、繊維産業や眼鏡枠産業、化学産業といった多様な既存産業の垣根を超えた産業横断的な分野でもある。
ところで、日本の場合、研究開発企業の割合は全体の8~10%程度といわれる。その中で、今回の企業調査でわかった2割にも及ぶ新製品・新サービス開発企業の割合は、非常に高いウエイトと言わざるを得ない。地域産業の歴史を振り返ると、例えば、繊維産業では、明治以降、シルクライク、ウールライクといった考え方をベースに天然繊維から化合繊織物の転換が進み、この地に合繊繊維を中心とした織物産地を誕生させた。眼鏡枠産業でも、真鍮(しんちゅう)→金・銀・銅・セルロイド→洋白・ハイニッケル→チタン・NT合金・マグネシウム亜鉛からマグネシウムまで素材の加工技術の開発が産地の発展を支えた。また、近年の地域中小製造業の技術力の高さは言うに及ばない。こうした中で、今回発生したコロナウイルス感染症は、ここで述べた地域製造業の産業特性、持ち前の開発力に火をつけたような気がする。
ならば、地域はこの「命を守る産業分野」を地域の新たな産業分野と位置づけ、育成することも必要ではないか。具体的には、「命を守る産業分野」参入に向けて頑張る企業へのものづくり・技術の高度化支援や、そのための金融支援、新製品・技術開発・サービス開発にまつわる情報提供・相談業務のさらなる充実が必要であり、合わせて昨今のデジタル化に向けた企業行動にも着目した支援も必要と考えられる。
その結果、地域産業の高付加価値化、労働生産性の向上を促し、最終的には産業構造の転換・高度化にもつながることを期待したい。「自由な貿易」から「公正な貿易」へ
コロナ後の世界経済は、ワシントンコンセンサスによるグローバリゼーションが推進される中で顕在化した「富の偏在」や「格差の拡大」の是正に向けた制度改革とともに、「自由な貿易」から「公正な貿易」へとパラダイムシフトが進む可能性がある。
そう思う理由は、いくつかある。まず、世界経済全体で見た所得再分配上の不平等があまりにも拡大している点だ。1980年と2016年の世界の家計所得の伸びを比較した調査によると、この間に増加した世界のトップ1%の所得は下位50%の2倍以上に及ぶ。また、別の調査によれば、世界でもっとも裕福な8人が保有する資産は、下位半分が保有する資産とほぼ同じだ。そして、そのうち6人が暮らす米国では、240万人に当たるトップ1%の富裕層が、数ではその50倍の労働者階級全体の倍の所得を手にするに至っている。最後の米国での調査においては、過去40年間で両グループへの富の配分は逆転したことも示されている。しかも、この間、労働者の実質賃金は殆ど変わっていないのだ。こうした事実は、自由化や規制緩和、さらには、富裕層や大企業への減税によって、富める者が富めば、いずれ、貧しい者にも富が浸透する、とした「トリクルダウン効果」はいつまで待っても現れないことを如実に示すこととなり、かつてないほどに人々の間に不平等感が募っているのである。
格差は国家間レベルでも広がっている。経済理論上は、自由貿易は競争力が弱い国においても、その国の中で比較優位性の高い分野に特化することで、社会的余剰(豊かさ)を増やすことができる、はずであった。しかし、現実には、グローバリゼーションの結果、急速に経済発展したのは、中国やASEANなどごく一部の新興・途上国に過ぎない。それは、貿易のメリットを途上国にもたらすには、市場アクセスだけでは不十分なためである。たとえば、EUでは、後発途上国(LDC)に対して、武器以外のすべての製品の輸入関税を免除する優遇制度(EBA)を採用しているが、EBA対象国であるタンザニアからEUへの輸出は増えていない。これは、後発途上国の輸出機会を活かすには、外資の導入などを通じた、生産能力の拡大や技術支援が必要なためである。この点において、アフリカにおける中国の一帯一路構想は、一定程度評価できる。しかし、「債務の罠」の問題を抜きにしても、アフリカへの援助に際して政治的な制約を課さない中国の姿勢には、アフリカ側に好意的な印象を与える一方で、アフリカ域内の汚職や人権侵害などを助長する恐れがあるとして危惧する声が上がっているのも事実である。
また、昨年、『ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)』に掲載された論文によると、環境に与える「富」の影響が深刻なレベルに達している。これまで、環境にもっとも大きな影響を与える要因は「消費」と「技術」だと考えられてきたが、ここ数十年で、豊かな国の消費者による「消費」が急拡大した結果、技術革新を通じて削減できるレベルを遥かに超えてしまったのである。つまり、地球上の生活に関連した温室効果ガス排出量の10%を約40億人の「世界における収入下位50%」が生み出しているのに対して、その100分の1に過ぎない4000万人の「世界でもっとも裕福な0.54%」が生み出す同排出量は14%に達しているのだ。さらに、先進国に住む多くの人が含まれる世界のトップ10%の富裕層は環境への影響のうち25~43%の責任を負っている。
ところで、不思議なのは、際限のない「富」への執着が社会的問題を引き起こしている、という点である。なぜなら、ある一定以上の水準を超えると、所得の伸びは幸福度の高まりに寄与しなくなる、とした「イースタリンのパラドックス」が示唆するように、これまで「富」への執着は所得の増加とともに薄れていくものと思われていたからである。しかし、今、現実の世界で起こっているのは「地位消費」(positional consumption)という概念による正反対のメカニズムである。即ち、人は基本的な欲求を満たすと、社会的希少性によって少数の人しか入手できない「地位財」(positional good)を求めだすというのだ。そう考えると、米ベンチャー企業が2022年に開業予定の「宇宙ホテル」への滞在料金が、12日間で10億円であるにもかかわらず、すでに、4か月先の予約まで完売というのも決して不思議ではない。しかし、今後、先進国の人々が一斉に地位財を求めだすと、地球環境の破壊はとめどなく加速していくことが懸念される。そのため、「もっとも裕福な人々に課税すること」や「弱いエコシステムと貧しい人々に投資すること」が必要とする同論文の主張は、ロールズの「正義」の概念とも合致しており、検討に値する。
次に、国際貿易に関して問題と思われるのは、アフリカにおける中国の「一帯一路」にみられるように、新興・途上国の中には、欧米先進国とは異なる価値観や慣習によって、開発や貿易を通じて人権侵害や環境破壊が行われている可能性があることだ。現行の国際ルールでは、たとえ、コスト削減のために人権侵害や環境汚染に加担しているとしても、それに対してペナルティを科すのは難しい。しかし、グローバリゼーションの制度的欠陥が鮮明となった今、世界経済秩序に関する新たな制度設計の構築が必要となっている。具体的には、「自由な貿易」から「公正な貿易」への変更・修正である。 では、「公正な貿易」とは何か。ダンピング関税を例に取ると、これまでは、結果としての価格の正当性がチェックされてきた。たとえば、中国のWTO加盟時に、貿易相手国は最長15年間、中国を「非市場経済」として扱うことが認められた。それによって、輸入国は中国からの輸入品に対して反ダンピング税を課すことが容易になった。コストの割高な国の生産費用を中国における生産費用として代用することができるためだ。現在、中国がすでにWTO加盟後15年を超えたことで、多くの国は中国に市場経済としての地位を与えているものの、米国とEU、そして日本は未だに認めていない。ただ、「市場経済」としての承認の遅れは、単に、貿易(覇権)戦争の悪化を招くだけとの指摘がある。そこで、これから目指す「公正な貿易」では、これまでのような、結果としての価格の正当性というよりも、そこに至る経緯が重要となってくる。換言すれば、「ソーシャルダンピング」や「エコロジカルダンピング」の概念を、国際的な貿易ルールの中に反映させるべき、ということである。実際、現在協議中の、中国とEUとの投資協定では、中国の人権問題も俎上に上がっている。また、EUは温暖化対策が不十分な国からの輸入品に価格を上乗せする「国際炭素税」を2023年までに導入する方針を打ち出している。こうした政策は輸入価格の上昇につながることから、消費者余剰(消費者の利益)を減らすとして反対意見が出ることが予想される。けれども、我々がほんの少し我慢することで、国際間の不平等や環境破壊が抑制され、世界全体の総余剰(万人の利益や満足感)は増えるのである。ならば、我慢した分だけ幸せを分かち合えると考え方を改めてはどうか。 以上第二回福井県企業の「コロナ禍での事業活動に関する緊急調査」結果報告書
福井県企業の「コロナ禍での事業活動に関する緊急調査」結果報告書
ふくい地域経済研究第32号
人の幸せを測る国際標準とは?
“0段目はあなたにとって「最低の生活」、10段目はあなたにとって「最高の生活」。あなたの生活は今、ハシゴのどの段階にいますか?”読者の皆様はこの質問に0-10のどの数字を選ぶだろうか。ぜひ一度、ご自身の中で回答してもらえればとおもう。
この質問は、人の幸せを測る現在の国際標準であり、キャントリルの階梯と呼ばれる方法だ。人生をハシゴと見立て、主観的な幸福度や満足度を測定する際に世界中で最も活用されている。例えば、国連機関が実施している世界幸福度調査(World Happiness Report)の世界ランキングも、この測定方法の結果に基づき公表され、マスコミを通じてそのランキングは注目の的となっている。最新の2020年の結果では、日本は153国中62位と低迷し、北欧諸国が上位を占めている。
当然ながら上位国の常連である北欧諸国から学ぶことは多く、また日本は「寛容度」や「人生における選択の自由度」など、改善しなくてはいけない課題があることに論を待たない。しかし同時に、人生をハシゴと見立て、上にあがればあがるほど幸せであるという考え方・測定方法は本当に国際標準として普遍的なものであるのか、ということには議論の余地が多分にある。
私自身はブータン王国で人の幸せを測るGNH調査にご一緒させてもらったが、その時に実感したことがある。ブータンのように中庸の文化を持つ国において、ハシゴにおける9や10を回答する者の割合は少ない。真ん中に位置する5を基準にしながら、よい状態と感じていれば、6や7を選ぶ傾向がある。2015年のブータンの調査では、この国際標準の質問での回答の平均値は6.88だった。また、調査において日常に感じている感情を尋ねる質問もあるが、ブータン人が感じてる一番多いポジティブな感情は「おもいやり(Compassion)」であった。刺激の強い高覚醒の幸せというよりも、平穏や安寧という言葉が似合う幸せの存在をブータンからは感じた。上にあがればあがるほどいいという価値観が幸せの唯一の源泉ではなく、文化的に必ずしも当てはまらない国も多いということを認識する必要がある。
そこで現在、日本の公益財団法⼈であるWell-being for Planet Earthを中心に、西洋の価値観だけでなく日本を含む多様な地域の価値観も尊重し、新しい国際基準となる幸せ(ウェルビーイング)の測定方法の検討を進めている。様々なテーマでの議論が続いているが、一番注目したいのが、人生の調和・ハーモニーやバランスがとれているという幸福感を測定することへの挑戦だ。現在の幸せ測定の国際標準をハシゴ型と捉えるのであれば、振り子型の調和やバランスを重視した測定方法と言える。
幸福度の議論はどうしても結果としてのランキングにのみ視線があつまってしまうが、ぜひ何をどのように測っているかにも一緒に注目してもらえれば嬉しい。福井県の在宅医療・介護と地域包括ケアシステム
わが国は、住み慣れた地域で自分らしい生活を維持・継続するために地域包括ケアシステムを推進している。福井県でも、在宅医療・介護を必要とする住民が安心して地域で療養生活を継続することができるよう、地域包括ケアシステムにおける在宅医療・介護連携をシステム化している。本コラムでは、「在宅医療・介護連携に関する市民アンケート調査」(大久保清子、2019年11月)結果の一部を紹介し、自宅で楽しく豊かな療養生活を送るために必要なポイントをお伝えしたい。
本調査は、2019年11月時点で福井県内に居住する市民約2,400名で、居住地や性別、年代(20~80歳代)を無作為に抽出した。回収1964部、回収率は82%である。男性22.4%、女性77.2%、不明0.4%で、40歳代が21.3%と最も多く、次が30歳代、50歳代の20.3%である。家族構成は、2世代世帯(子ども)33.7%、3世代世帯21.9%、夫婦のみ世帯15.6%、2世代世帯(親)13.6%、単身世帯12.1%であった。
回答者が感じている「自宅で療養するときの不安」は、「精神的な負担」が79.0%と最も多く、次に「経済的な負担」70.8%、「仕事と介護の両立」48.9%であった。医療や介護に関する身近な相談相手で最も多いのが「家族」88.8%で、次に「友人・知人」40.1%であった。在宅医療を実現できない・希望しない理由で最も多かったのは、「介護する家族に負担がかかる」83.3%であった。しかし、人生の最期を迎えたい場所は「自宅」が48.4%と最も多く、次が「ホスピスなどの緩和ケア施設」23.0%であった。在宅医療の認知度で見ると、在宅医療を良く知っている人の方が自宅で最期を迎えたいと考える割合が高く、余命で大事にしたいことは、「家族や友人のそばにいること」71.2%、「家族の負担にならないこと」67.0%、「痛みや苦しみがないこと」61・0%であった。
この結果をみると、県民は家族や友人をとても大事にしており、最期まで家族や友人とかかわりながら自宅で療養生活を送りたいと思っているようである。しかし、家族に負担をかけない、痛みや苦しみを軽減するため施設に入所しようと考えていると思われる。在宅医療は、訪問看護や介護などの多職種や近隣住民とも連携し、その人・その家族らしい療養生活を支えていくものである。在宅医療を良く知っている人が自宅で最期を迎えたいと考える割合が高いのは、それができることを知っているからであろう。自宅で医療や看護・介護を必要とする方は、自分一人ですべてを抱え込むのではなく、日常的なケアは在宅医療や看護・介護の専門職に任せ、家族や友人が楽しく過ごすための豊かな時間と空間をつくってみてはどうだろう。その実現に向け、近隣の訪問診療や訪問看護・介護事業所、地域包括支援センター等に相談し、福井県の多職種連携システムを活用して欲しい。